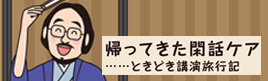- HOME
- 2020年1月号
2020年1月号
2020年1月号の巻頭では、「保健師の業務を効果的・効率的に進める」─統括保健師は何をすべきか と題し、新春座談会をお届けする。現場の保健師からは「事業をこなすことでとにかく忙しい」「地域に出る時間がない」という悲鳴がよく聞こえてくるが、座談会では行政学の視点も参考に、統括保健師の果たすべき役割についてそれぞれの立場から語ってもらった。
特集は「子どもの自殺を防ぐ 10代を中心に」。全体の自殺死亡率が減少する中で、子どもの自殺率は変わらない。さらに10~14歳に限ってみれば自殺率は増加しているのが現状で、依然として深刻な状況にある。1月号では実態と対策についてまとめた。
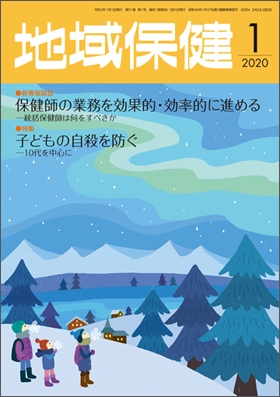
新春座談会保健師の業務を効果的・効率的に進める─統括保健師は何をすべきか

◎新春座談会 保健師の業務を効果的・効率的に進める─統括保健師は何をすべきか
「事業をこなすことでとにかく忙しい」「地域に出る時間がない」
──現場の保健師からはこんな悲鳴が聞こえてくる。
現場に降りてくる事業は合計で100を超え、事務的な作業だけで保健師の手が塞がっているという不幸な状況は、かねてから指摘されてきた。
民間企業では、企業目的(収益を上げる)を達成するために、効果的・効率的な業務体制づくりが進んでおり、行政学では民間の優れた経営理念や経営手法を積極的に取り入れた「行政経営」の考え方もある。また、地域を越えた自治体全体の健康課題を把握し、当該自治体で働く保健師の業務を俯瞰して関連づけ、総合的に推進するのは統括保健師の役割である。
新春座談会では、保健師の業務を効果的・効率的に進めるために、行政学の視点も参考に統括保健師の果たすべき役割を考える。
(座談会出席者)
加藤典子さん(厚生労働省健康局健康課保健指導室)=司会
春山早苗さん(自治医科大学看護学部)
真山達志さん(同志社大学政策学部)
林 礼子さん(島根県健康福祉部、統括保健師)
村川実加さん(磐田市健康福祉部、統括保健師)
特集子どもの自殺を防ぐ 10代を中心に
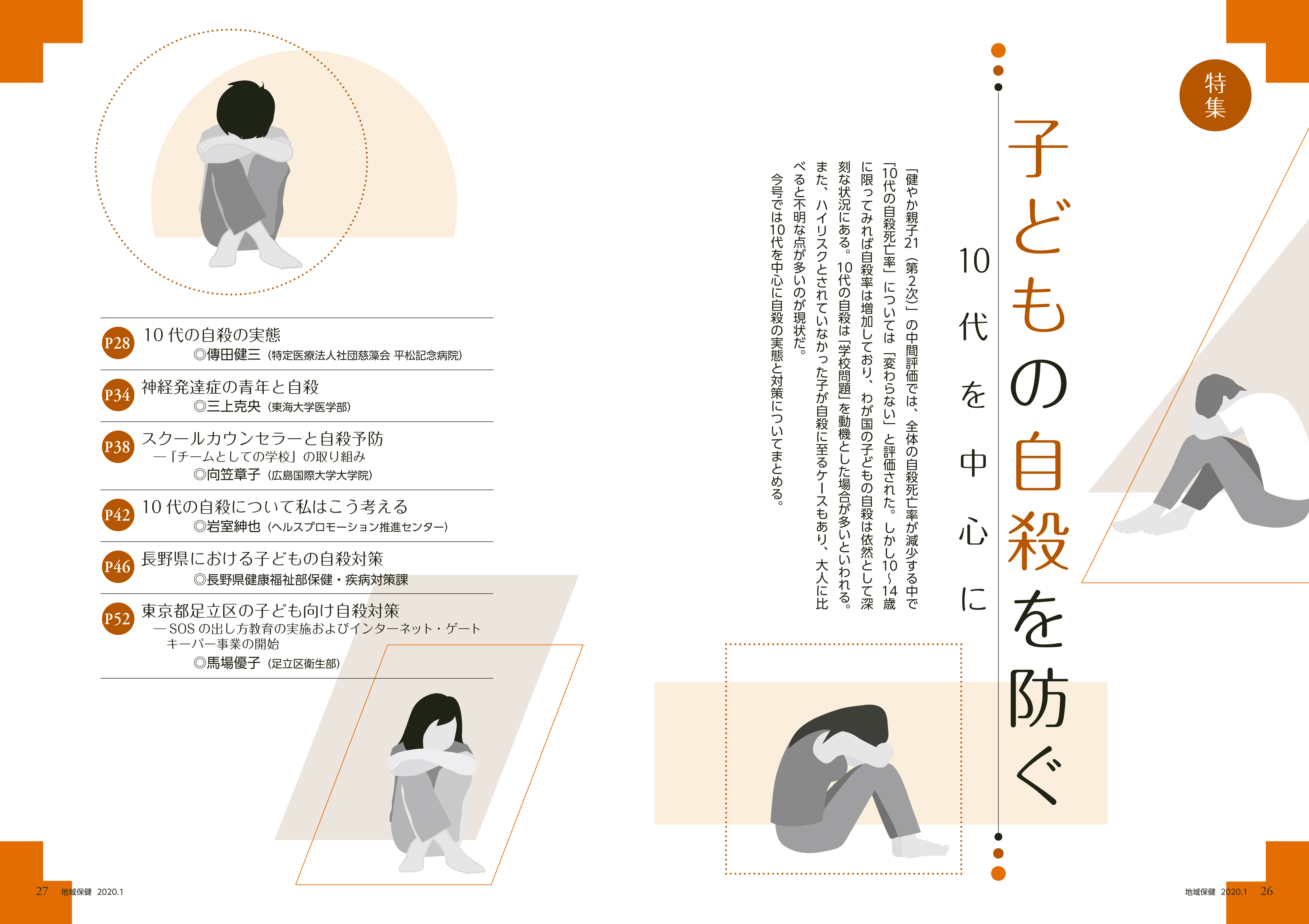
「健やか親子21(第2次)」の中間評価では、全体の自殺死亡率が減少する中で「10代の自殺死亡率」については「変わらない」と評価された。
しかし10~14歳に限ってみれば自殺率は増加しており、わが国の子どもの自殺は依然として深刻な状況にある。10代の自殺は「学校問題」を動機とした場合が多いといわれる。また、ハイリスクとされていなかった子が自殺に至るケースもあり、大人に比べると不明な点が多いのが現状だ。
今号では10代を中心に自殺の実態と対策についてまとめる。
◎10代の自殺の実態
傳田健三氏(特定医療法人社団慈藻会 平松記念病院)
◎神経発達症の青年と自殺
三上克央氏(東海大学医学部)
◎10代の自殺について私はこう考える
岩室紳也氏(ヘルスプロモーション推進センター)
◎長野県における子どもの自殺対策
長野県健康福祉部保健・疾病対策課
◎スクールカウンセラーと自殺予防─「チームとしての学校」の取り組み
向笠章子氏(広島国際大学大学院)
◎東京都足立区の子ども向け自殺対策─ SOSの出し方教育の実施 およびインターネット・ゲートキーパー事業の開始
馬場優子氏(足立区衛生部)
ひよこ、ホップ、ステップ、ジャンプ!
井筒 迅さん 大杉成美さん(杉並区立高井戸保健センター)
ピープル
森田眞希さん(NPO法人 地域の寄り合い所 また明日 代表)
連載
いのちに向き合う
第5回 妹の死と喪の作業(後篇)
浜垣誠司
生活習慣を変えるコミュニケーション技術
第5回 子育てと動機づけ面接(トーマスゴードンのモデル)
磯村 毅
罪を犯した人の生活と健康支援
第5回 増加している高齢犯罪者 ─ 地域の保健師に求められる視点
舩山健二
虐待予防は母子保健から 指導ではなく支援
第5回 虐待ハイリスクの親を支援するグループ
鷲山拓男
ESSAY国際保健
第35回 ワシントンD.C.のウォーターゲートと米大統領弾劾
松田正己
保健師のための閑話ケア
第86回 ねずみの話
藤本裕明
中臣さんの環境衛生ウオッチング
第71回 災害時の大規模停電
中臣昌広