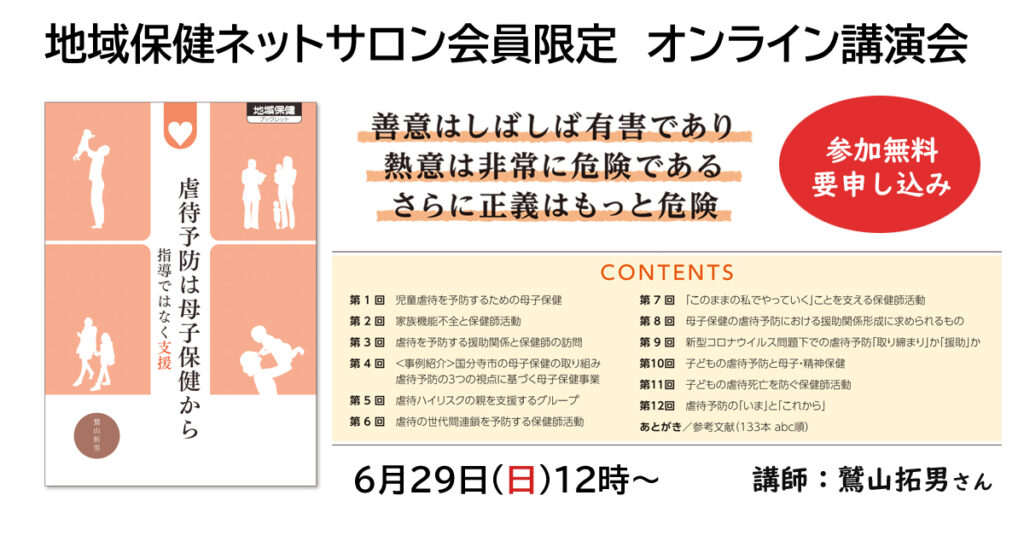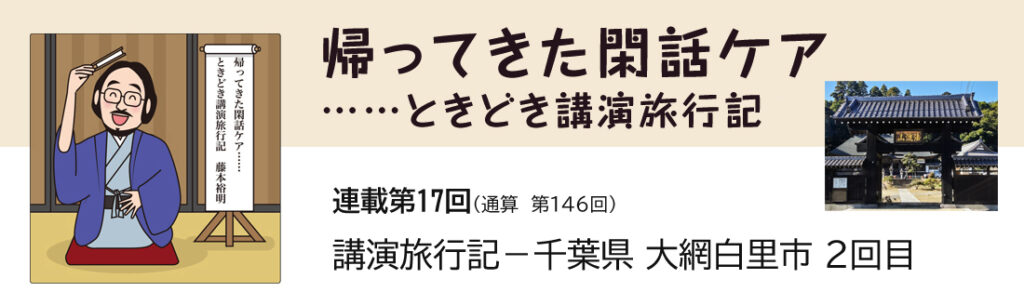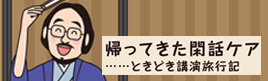- HOME
- 地域保健アーカイブ
地域保健アーカイブとは
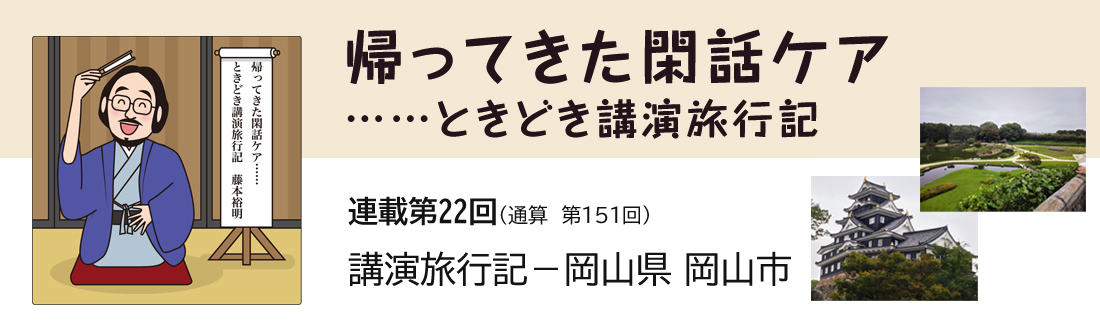
47都道府県のうち、23番目の講演訪問地は岡山県の岡山市。
個人的にも伺った事がない土地だ。中国地方を中国5県と呼ぶそうだが、2017年2月、全国保健師長会山口県支部からのお招きで山口県にお伺いして以来の中国地方という事になる。
岡山県訪問の布石は2023年4月にさかのぼる。その前月の3月号が雑誌「地域保健」の休刊前の最終号だったが、そこに私はこう書いた。
「2011年1月から、欠かさず読んでいるなんていう方は、いらっしゃるだろうか? 証明のしようはないだろうが、もし、いらっしゃったら自己申告で良いので、相談室にでも編集部にでもご一報下さい。何らかの形で御礼をしたいと思う。ん? 全部じゃないが50回以上は読んでいる? うんうん、そんなあなたも、是非ご一報下さい。何か御礼を考えます」
それをお読みになった岡山市のTさんが……(続く)
<著者プロフィール>
藤本裕明(あさか台相談室)
分類学上は霊長目ヒト科の♂。立場上は一応、心理カウンセラーに属する。自分の所の他、埼玉県川越市の岸病院・さいたま市の小原クリニックなどで40年以上の臨床経験があるが、年数だけで蓄積はおそらく無い。むしろ、蓄積より忘却が確実に増している。
なかなか秋が来なくて、秋らしい日が来たと思ったら、急に晩秋になり、時々冬が顔を出してくる。本当に困った季節変化だ。高齢化で適応能力が下がっているところにこの気候の状態は、やはりしんどい。お若い皆さんも油断なさらずくれぐれもご自愛を!
●あさか台相談室 公式サイト
https://www.asakadai-saitama.com/
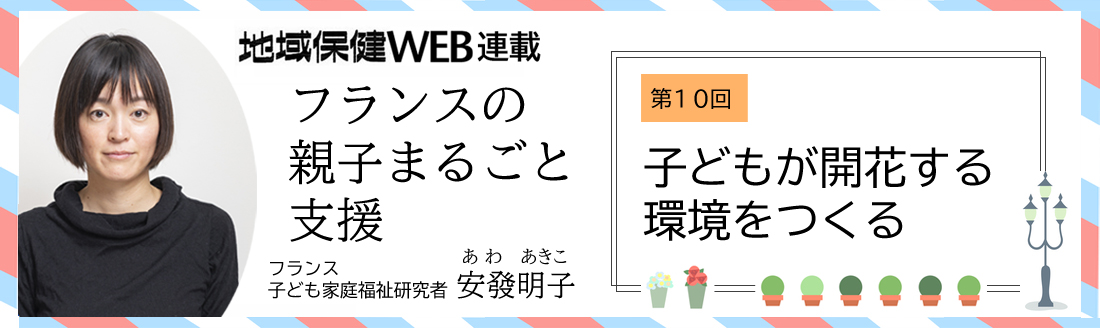
WHOは2012年にウェルビーイングを「良い心身の健康状態、頼れる人がいること、家族の安定性、周りの人を信頼できること」と定めている。子どもの権利条約にもフランス語訳には「ウェルビーイングに必要なケアや医療を国が保障する」とある(日本政府訳は「福祉に必要な保護及び養護を確保する」)。ウェルビーイングはフランス語で「bien-être(良い、在る)」という言葉で子どもでも日常的に使う身近な言葉だ。逆は「mal-être(悪い、在る)」で、無口だったり勉強に集中できなかったり意地悪なことをしたりといった状況を指す。大人たちは子どもについて「悪い、在る」が観察されたとき支援をスタートさせ放置しない。成績よりも心理的健康の方が大事であるという取り組みは2011年より一貫して続けられてきており、3歳以上の子どものウェルビーイングの状況について国立保健機構が調査もしている。
フランスで教育の目的は「開花」である。花が開くことができるように環境を大人が整えるというイメージだ。「自立」という言葉も日仏で使われるが、その道のりは違って語られる。日本では経済力を身につけ自分でできるようになること、フランスでは自尊心が十分育ち、自分の関心があることを見つけるというステップがあった先の仕事や暮らしと考えられている。
<著者プロフィール>
安發明子(あわ・あきこ)
フランス子ども家庭福祉研究者。ソーシャルワーカー養成校AFRISパリ理事。 立命館大学大学院人間科学博士、EHESSフランス国立社会科学高等研究院健康社会政策学修士、社会学修士、一橋大学社会学学士。 首都圏で生活保護ワーカーとして勤務したのち2011年渡仏。 子どもが幸せに育つための文化の醸成に取り組んでいる。著作『一人ひとりに届ける福祉が支える フランスの子どもの育ちと家族』(2023)かもがわ出版、翻訳書『ターラの夢見た家族生活 親子まるごと支えるフランスの在宅教育支援』(2024)サウザンブックス、『NOと言えるようになるための絵本』(2025)ゆまに書房。
- 安發明子さん公式サイトはこちら
https://akikoawa.com/

5歳児健診の話題をあちこちで耳にするようになりました。就学時健診だけでは拾いきれない小さなサインを、もう一歩手前の時期に共有し、家庭・園・医療・福祉・教育へ橋を架ける、そのための体制づくりがまさに今動いているのを感じます。
こうした変化に伴い、本年、5歳児健診の時期のことばの発達をテーマにした講演のご依頼があったり、周囲の母子保健関係者の方から「発音の幼さは様子見でよいか」「吃音(きつおん)がある子はどうすればよいか」「集団で指示が入りにくい子への声かけはどう具体化するか」「文字読みや音韻意識の芽生えは健診でどこまで見ればよいか」といったご相談を受けたりすることが増えました。地域はさまざまでも現場が直面する迷いのポイントは共通しており、この時期に共通したことばのお悩みが見えてくるようで興味深いものです。
<著者プロフィール>
寺田 奈々(ことばの相談室ことり 言語聴覚士)
慶應義塾大学文学部卒。養成課程で言語聴覚士免許を取得。総合病院、プライベートのクリニック、専門学校、区立障害者福祉センターなどに勤務。年間100 症例以上のことばの相談・支援に携わる。専門は、ことばの発達全般・吃音・発音指導・学習面のサポート・失語症・大人の発音矯正。著書に『子どもとのコミュニケーションがどんどん増える! 0~4歳 ことばをひきだす親子あそび』(小学館)、『発達障害&グレーゾーン幼児のことばを引き出す遊び53』(誠文堂新光社)。
●ことばの相談室ことり 公式サイト
https://stkotori.com/
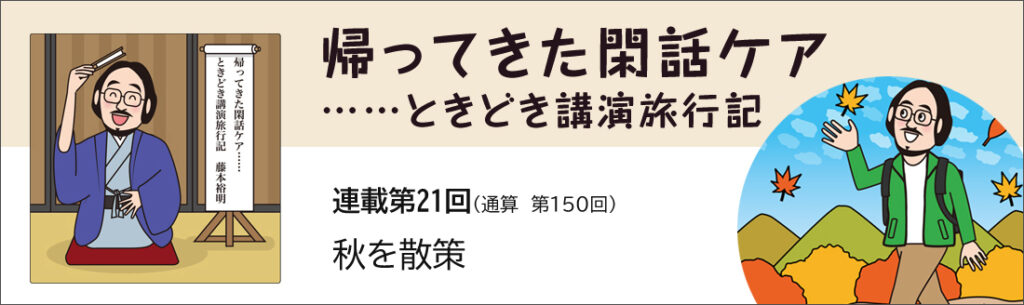
今年も残すところ、あと2か月ちょっと。実りの秋も盛りを過ぎて自然界は冬支度に入ろうとしている。木々は実を落とし、そろそろ紅葉色に着替える準備をしていて、北国や山では、もうすでにそれが始まっていて、日差しは明るくても空気は冷たくて、人々は、あ、そろそろコートやマフラーの準備をしなくちゃって思う。
そんな秋。
……あれ? そんな秋に、ここ何年も出会ってない気がする。たしかに、米は実り、梨、ブドウ、柿、栗は市場に出回ってはいる。でも、……(続く)
<著者プロフィール>
藤本裕明(あさか台相談室)
分類学上は霊長目ヒト科の♂。立場上は一応、心理カウンセラーに属する。自分の所の他、埼玉県川越市の岸病院・さいたま市の小原クリニックなどで40年以上の臨床経験があるが、年数だけで蓄積はおそらく無い。むしろ、蓄積より忘却が増している気がする。
なんと、福井県からお声がかかった! これで24番目になるので、実現すれば講演旅行訪問地が全都道府県の過半数になる! 来年2月なので、それまでは山道歩いて転んだりしないで、何とか健康を維持しなくては。次の目標はいよいよ全国制覇―なんて面白がって言う方もいらっしゃるが、2011年の連載開始からざっと15年かかっての24番目である。さらにあと15年…。
●あさか台相談室 公式サイト
https://www.asakadai-saitama.com/
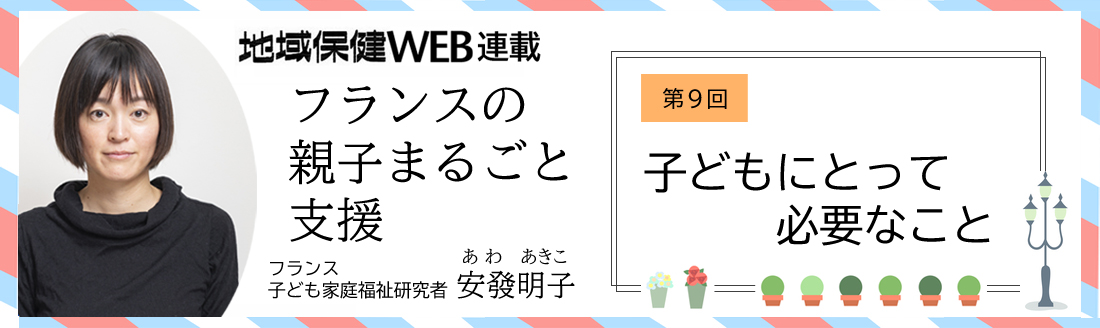
子どもが元気に育つにはどのような条件が必要か、すでに多くのことが科学的に分かっている。分かっている以上、運任せにするのではなく、平等に子どもの育ちを支える国をつくりたい。つまり、子どもにとって必要なことを社会的に対応する仕組みを構築する必要がある。知識を文化として広め、全ての子どものニーズが満たされるよう、関わる大人たち一人一人が気にかけ、行動し、解決するまで見届ける。「家に食べるものがないんだって」「叩かれたらしいよ」と知ったら放置せず、声を掛け、支える。それは親を罰することなく行うことができる。
フランスでは「親をすること」を就職したばかりの新人職員に例えることがある。新人職員に対して、「ミッションはこれ」と伝えたきり、放置することはない。「手伝ってほしいことがあったら……
<著者プロフィール>
安發明子(あわ・あきこ)
フランス子ども家庭福祉研究者。ソーシャルワーカー養成校AFRISパリ理事。 立命館大学大学院人間科学博士、EHESSフランス国立社会科学高等研究院健康社会政策学修士、社会学修士、一橋大学社会学学士。 首都圏で生活保護ワーカーとして勤務したのち2011年渡仏。 子どもが幸せに育つための文化の醸成に取り組んでいる。著作『一人ひとりに届ける福祉が支える フランスの子どもの育ちと家族』(2023)かもがわ出版、翻訳書『ターラの夢見た家族生活 親子まるごと支えるフランスの在宅教育支援』(2024)サウザンブックス、『NOと言えるようになるための絵本』(2025)ゆまに書房。
- 安發明子さん公式サイト
https://akikoawa.com/

子育てを始めてから、日常のあちこちで「赤ちゃんのことば」にまつわるさまざまな表現に出会うようになりました。保護者の方や支援に関わる人たちが自然に使っている用語の中には、私たち言語聴覚士が臨床で想定しているものとは異なるニュアンスで使用されているものもあります。時に予想外のことばの使い方が広がっていることを知り、「へえ」と感心することもしばしば。
もちろん、それが大きな問題につながるわけではありませんし、温かいまなざしのこもった呼び方ばかりです。でも、日常で交わされることばの使い方と、臨床での専門用語。その間には小さなすれ違いがあり、それを知ることで理解が深まります。せっかくなら専門用語のほうも、これを機会にお伝えしたいと思います。そこで今回は、身近でよく耳にする言い回しと専門的な用語をあわせて4つ、紹介してみたいと思います。
<著者プロフィール>
寺田 奈々(ことばの相談室ことり 言語聴覚士)
慶應義塾大学文学部卒。養成課程で言語聴覚士免許を取得。総合病院、プライベートのクリニック、専門学校、区立障害者福祉センターなどに勤務。年間100 症例以上のことばの相談・支援に携わる。専門は、ことばの発達全般・吃音・発音指導・学習面のサポート・失語症・大人の発音矯正。著書に『子どもとのコミュニケーションがどんどん増える! 0~4歳 ことばをひきだす親子あそび』(小学館)、『発達障害&グレーゾーン幼児のことばを引き出す遊び53』(誠文堂新光社)。
●ことばの相談室ことり 公式サイト
https://stkotori.com/
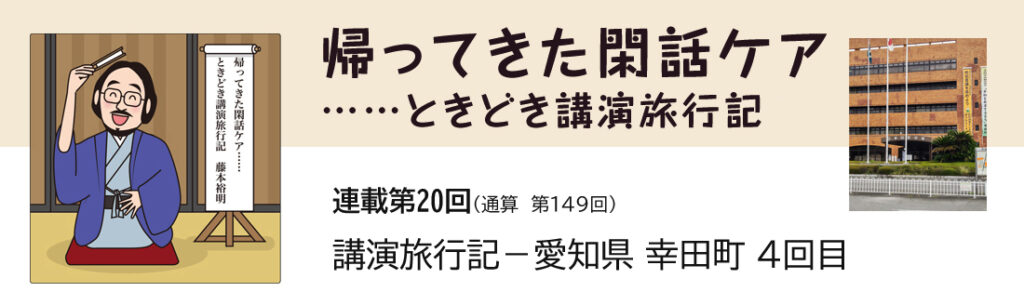
愛知県額田郡幸田町(ぬかたぐんこうたちょう)。皆さんも読めるようになったかな。3年連続4回目の訪問であり、旅行記としては去年の10月訪問を書いた今年の1月以来である。
高校生向け、市民向け、勤労者向けとやったから、そろそろネタが無くなりそうなものだが、今度は支援者向けに精神の話を―という依頼。同一市町村で地元を除く最多は、岩手県岩泉町の5回があるが、それに次ぐ4回目である。
支援者って、だったら、精神とかも学んでいるんじゃないかと思ったが、例えば……(続く)
<著者プロフィール>
藤本裕明(あさか台相談室)
分類学上は霊長目ヒト科の♂。立場上は一応、心理カウンセラーに属する。自分の所の他、埼玉県川越市の岸病院・さいたま市の小原クリニックなどで40年以上の臨床経験があるが、年数だけで蓄積はおそらく無い。むしろ、蓄積より忘却が確実に増している。
それにしても、今夏も暑かった。まだ終わってないけど。9月いっぱいくらいまだまだ猛暑日が出てくるかもしれない。今のところ米は順調みたいだけど、他の作物への影響も確実にあるだろうな。
困った時代になってしまった。やっぱり江戸時代の方が住みやすそう。
●あさか台相談室 公式サイト
https://www.asakadai-saitama.com/

■ 開催日時
2025年9月27日(土) 13:30~17:00(開場12:30)
■ 会場
株式会社 シンゾーン 本社ショールーム
東京都渋谷区渋谷4-1-18南青山ノグチビル2F
COMPANY – Shinzone
■ 参加費
無料
■ 定員
先着50名
■ 申し込み締め切り
2025年9月23日(火・祝)

■ 開催日時
2025年8月30日(土)20:00~
■ 開催方法
オンライン(Zoomミーティング)
■ 対象者
保健師を目指す方・新任期保健師
ご興味のある方ならどなたでも大歓迎!
■ お申し込み締め切り
2025年8月23日(土)
■ 問い合わせ先
FIRST DOOR事務局
公式サイト:https://firstdoor.studio.site/

本記事では、フランスの福祉現場で、働き手がウェルビーイングを保ちながらいかに成長を続けられるかについて、実践的な方法やチーム・組織全体での取り組み、工夫がされているかを紹介する。読者の皆さんの分野でも、働き手の健康とモチベーションの維持を支えることが、支援の質の向上に直結するといわれているのではないだろうか。バーンアウト予防として「働き続けることが喜びとなる環境づくり」のヒントに役立ててほしい。
<著者プロフィール>
安發明子(あわ・あきこ)
フランス子ども家庭福祉研究者。1981年鹿児島生まれ。2005年一橋大学社会学部卒、 首都圏で生活保護ワーカーとして働いた後2011年渡仏。2018年フランス国立社会科学高等研究院健康社会政策学修士、2019年フランス国立社会科学高等研究院社会学修士。フランスの子ども家庭福祉分野の調査をしながら日本へ発信を続けている。全ての子どもたちが幸せな子ども時代を過ごし、チャンスがある社会を目指して活動中。
●安發明子さん公式サイト
https://akikoawa.com/

ことばの発達について悩む保護者の方へ、「読み聞かせ」や「ことば掛け」といったアドバイスはよく耳にするかもしれません。しかし、本当にそれだけで十分なのでしょうか? この回では、絵本の「読み聞かせ」や「ことば掛け」にこだわりすぎることなく、子どもの特性や発達段階に合わせた関わりの大切さについて、言語聴覚士としての経験を交えながら考えていきます。
<著者プロフィール>
寺田 奈々(ことばの相談室ことり 言語聴覚士)
慶應義塾大学文学部卒。養成課程で言語聴覚士免許を取得。総合病院、プライベートのクリニック、専門学校、区立障害者福祉センターなどに勤務。年間100 症例以上のことばの相談・支援に携わる。専門は、ことばの発達全般・吃音・発音指導・学習面のサポート・失語症・大人の発音矯正。著書に『子どもとのコミュニケーションがどんどん増える! 0~4歳 ことばをひきだす親子あそび』(小学館)、『発達障害&グレーゾーン幼児のことばを引き出す遊び53』(誠文堂新光社)。
●ことばの相談室ことり 公式サイト
https://stkotori.com/
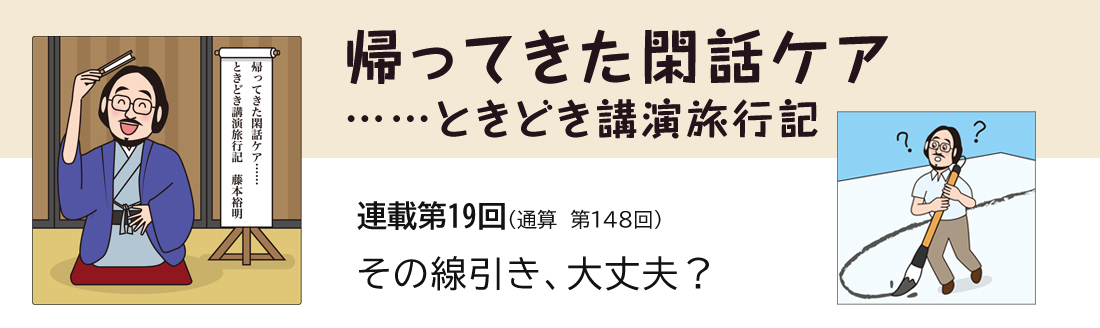
気象庁が関東地方の梅雨入りを発表した翌週くらいから、雨は全くなくて各地で猛暑日続出…。
はい、この日から梅雨の時期に入ったと、線を引いた途端にこれだ。もっとも、昨今の発表の仕方は、「梅雨入りしたとみられる」という表現で、後でいくらでも修正できるような発表になっているから、線引き、というほどのものでもないかもしれないが。
世の中にはいろいろな線引きがある。学生時代には、例えば100点満点で60点以上が合格点、59点以下は赤点なんていうのがあった。優秀な皆さんはそんな事で苦しんだ事はないかもしれないが、自慢じゃないがここだけの話……(続く)
<著者プロフィール>
藤本裕明(あさか台相談室)
分類学上は霊長目ヒト科の♂。立場上は一応、心理カウンセラーに属する。自分の所の他、埼玉県川越市の岸病院・さいたま市の小原クリニックなどで40年以上の臨床経験があるが、年数だけで蓄積はおそらく無い。むしろ、蓄積より忘却が増している気がする。
秋に、岡山県で喋る事になった! 23番目の都道府県である。いよいよ過半数まであとひとつなのだが、今年は今のところ、4回目の愛知県幸田町と岡山県しか本誌関連がない。年度内に本誌関連以外があと3つあるだけだ。どこかに物好きな自治体はないかなぁ…。
●あさか台相談室 公式サイト
https://www.asakadai-saitama.com/
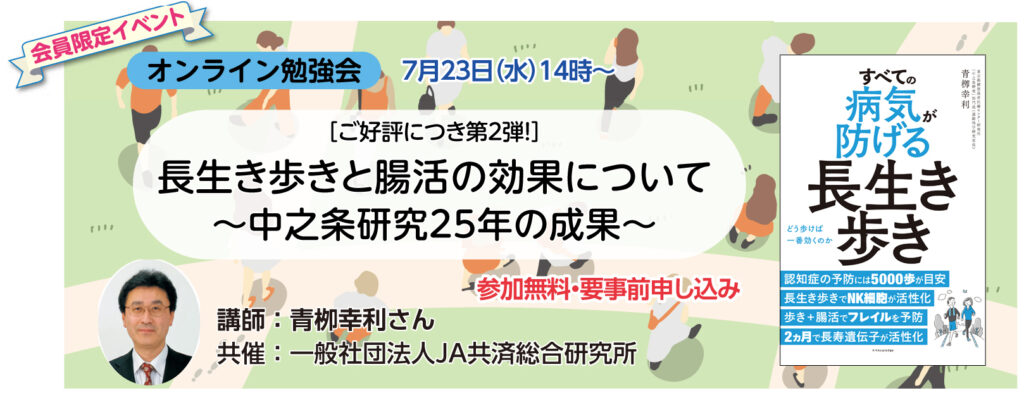
勉強会第2弾のお申し込み完了画面から、第1回の勉強会のアーカイブ動画をご覧になれます。参加後アンケートにご回答後、ご希望の方には第1回の講演、話題提供の資料をお送りしております。そちらもご活用ください。
【第1回勉強会(1/28)開催レポート】
いまあらためてウォーキング「奇跡の中之条研究」に学ぶ速歩健康法
第1回の勉強会の開催レポートを作成しました。参加後アンケートからいくつか感想もご紹介していますので、以下リンクよりご覧ください。
【おすすめの本】
著者:青栁幸利/四六判/144頁/1,430円(税込)/X-Knowledge
健康のために歩くとよいとされている歩数をご存じですか?
青栁幸利さんが長年の中之条研究から導きだしたのが、1日8000歩・中強度の運動20分という黄金律。医療費適正化にも役立つ「長生き歩き」についての最新情報と、意外かつ面白い新常識を一挙にまとめた一冊です。
本勉強会の予習・復習におすすめです。

なるかわしんごさん原画展の会場となった吉祥寺の「あぷりこっとつりー」さんは、絵本と雑貨の専門店。国内外の新刊&古本を合わせ3000冊以上展示されているそうです。そのお店のあちこちに、なるかわしんごさんの優しいタッチの絵本原画が飾られていました。上の写真はお店の一角に展示されていた原画とグッズのコーナーです。

ステッカーや車用の赤ちゃんの乗車サインなど、編集部でもいくつか入手してきました! なるかわさんの作品集には、その場でご本人がイラストを描いてくださいました。
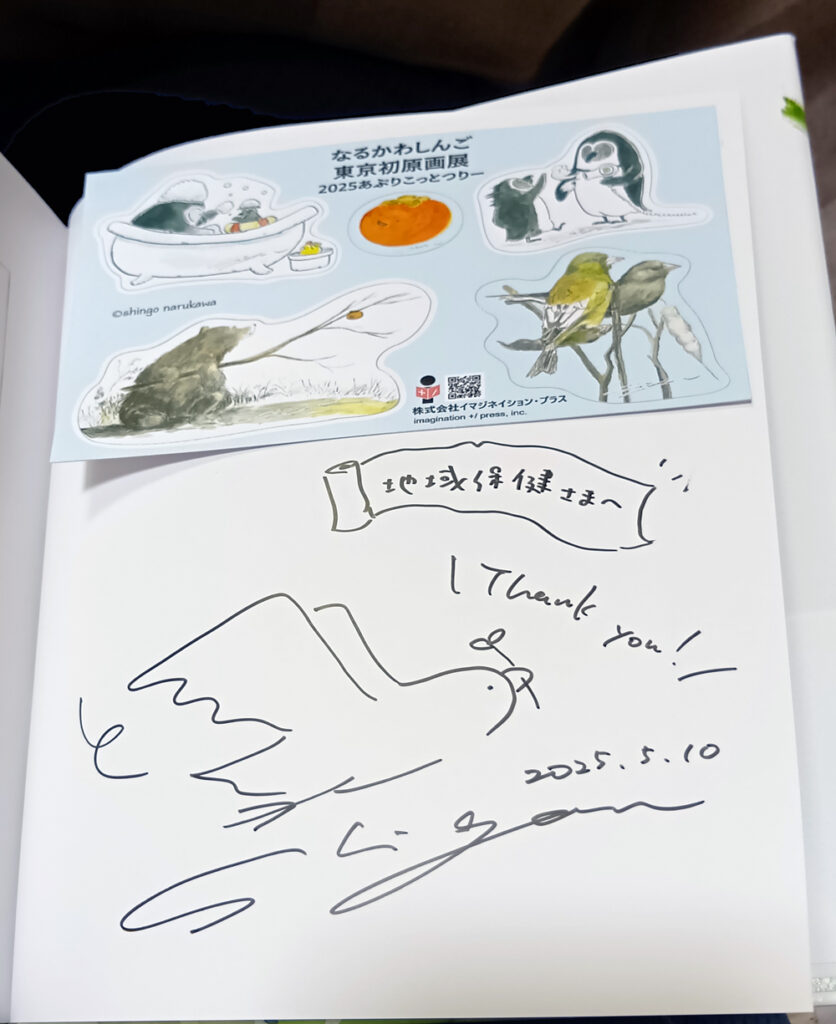
店内ではなるかわさんの絵本の販売もあり、編集部ではまだ持っていなかった『ちいさな しまの とりの おはなし』(イマジネイション・プラス)を購入。こちらにもサインをいただきましたのでご紹介します。

絵本作家・なるかわしんごさん(2025.5.10編集部撮影)
編集部では地域保健WEB版5月号の表紙のことで、たびたびなるかわさんと連絡をとりあっていましたが、直接お目にかかったのは久しぶり。なるかわさんには、展示会場となった「あぷりこっとつりー」のオーナーさんとの出会いや、作品にまつわるエピソードなど、短い時間でしたがいろいろとお話を伺うことができました。なるかわさんのお人柄や、さまざまなテーマにじっくり向き合う姿勢などが作品から伝わってきます。この後、会場ではなるかわしんごさんの講演会が開催され、たくさんの人が来場されていました。
地域保健WEBでこれから描いてもらうなるかわさんの絵も、皆さまどうぞ楽しみにしていてください。
なるかわしんごさんの地域保健(2022年9月号)のインタビュー
「ピープル」をWEBでご覧になれます。
なるかわしんごさんの絵本
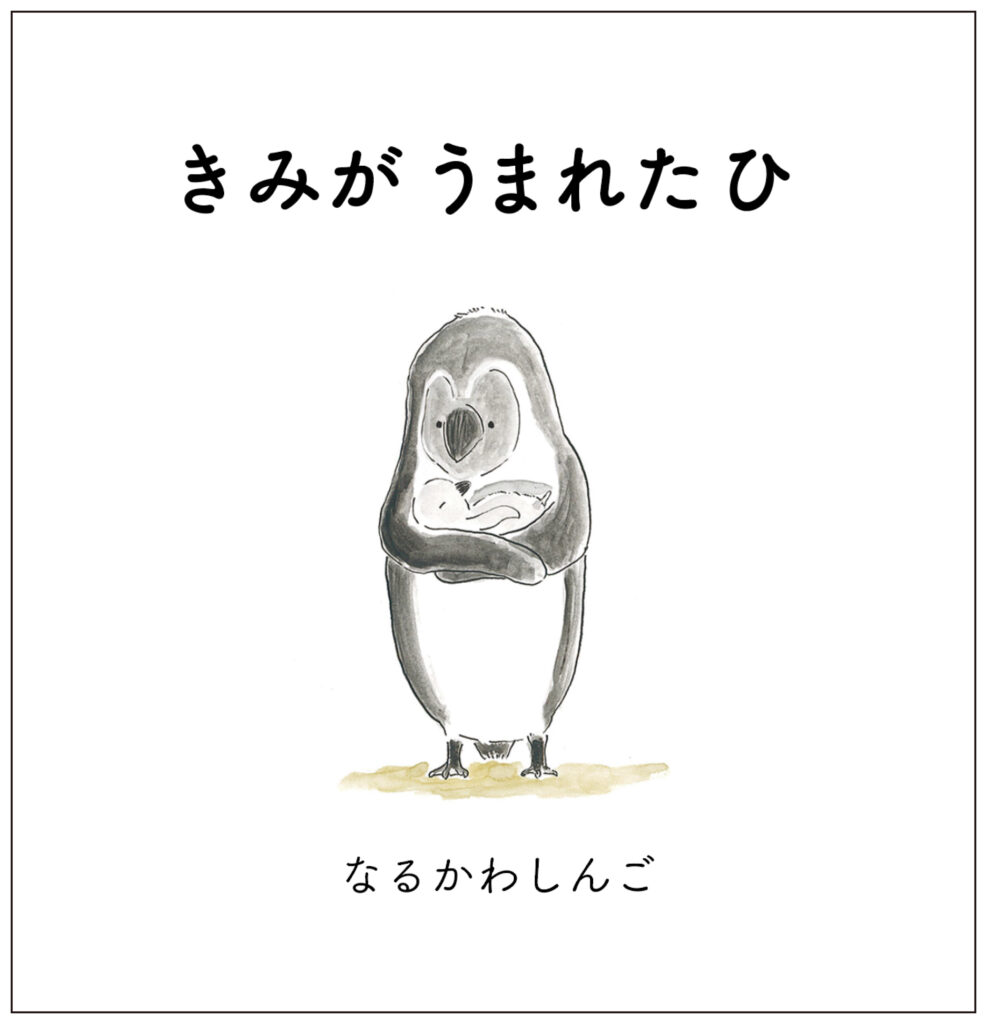
絵・文:なるかわ しんご/230 x 235 x 10mm/40頁/1,870円(税込)/イマジネイション・プラス
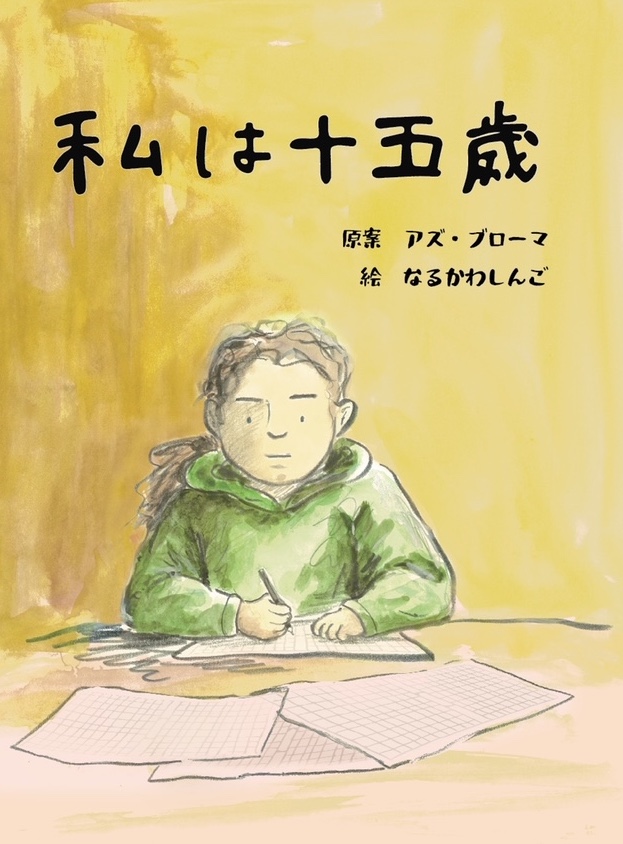
『私は十五歳』
文:アズ・ブローマ/絵:なるかわ しんご/監修: 駒井 知会・指宿 昭一/制作:中川 たかこ/215 x 275 x 10mm/40頁/1,870円(税込)/イマジネイション・プラス
ほかにも素敵な絵本がたくさんあります。
イマジネイション・プラスさん公式サイトもぜひご覧ください。
https://imaginationpluspress.com/booklist/
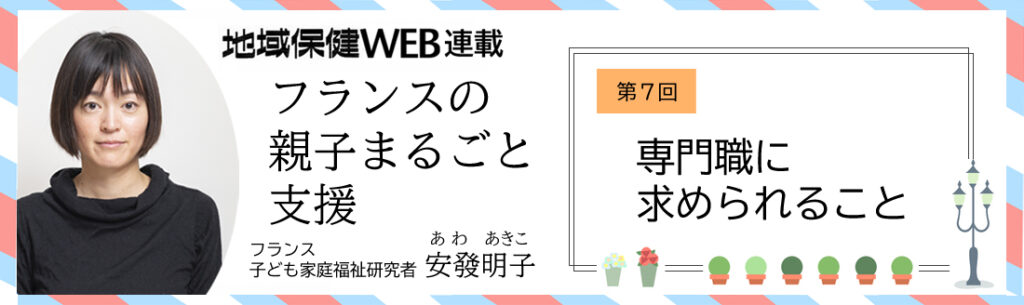
フランスでは、福祉の専門職とは単に知識を持つ人ではなく、支援を必要としている当事者が自分に適した解決策を自身で見出すことを支援し、利用者主体で関わることができる「あり方」が重要視される。特に「温かい見守り」と「ジャッジしない姿勢」が鍵となる。家族支援においては、専門職同士の連携や継続研修による持続的な知識・技術のアップデートが不可欠である。フランスの福祉現場では、ボトムアップによる発展が特徴であり、現場発の取り組みが全国に広がる文化が根づいていることを紹介する。
<著者プロフィール>
安發明子(あわ・あきこ)
フランス子ども家庭福祉研究者。1981年鹿児島生まれ。2005年一橋大学社会学部卒、 首都圏で生活保護ワーカーとして働いた後2011年渡仏。2018年フランス国立社会科学高等研究院健康社会政策学修士、2019年フランス国立社会科学高等研究院社会学修士。フランスの子ども家庭福祉分野の調査をしながら日本へ発信を続けている。全ての子どもたちが幸せな子ども時代を過ごし、チャンスがある社会を目指して活動中。
●安發明子さん公式サイト
https://akikoawa.com/

WEB連載「なな先生のことばの発達教室」が始まった頃にはまだ生まれたての赤ちゃんだったうちの息子も、いつのまにか1歳半を過ぎました。
毎日が、新鮮な驚きと発見の連続です。
そんな日々の中で、今回はうちの息子のことばが育っていく様子を見守りながら、「文を理解する」「文を話す」力の育ちについて、一緒に考えてみたいと思います。
<著者プロフィール>
寺田 奈々(ことばの相談室ことり 言語聴覚士)
慶應義塾大学文学部卒。養成課程で言語聴覚士免許を取得。総合病院、プライベートのクリニック、専門学校、区立障害者福祉センターなどに勤務。年間100 症例以上のことばの相談・支援に携わる。専門は、ことばの発達全般・吃音・発音指導・学習面のサポート・失語症・大人の発音矯正。著書に『子どもとのコミュニケーションがどんどん増える! 0~4歳 ことばをひきだす親子あそび』(小学館)、『発達障害&グレーゾーン幼児のことばを引き出す遊び53』(誠文堂新光社)。
●ことばの相談室ことり 公式サイト
https://stkotori.com/
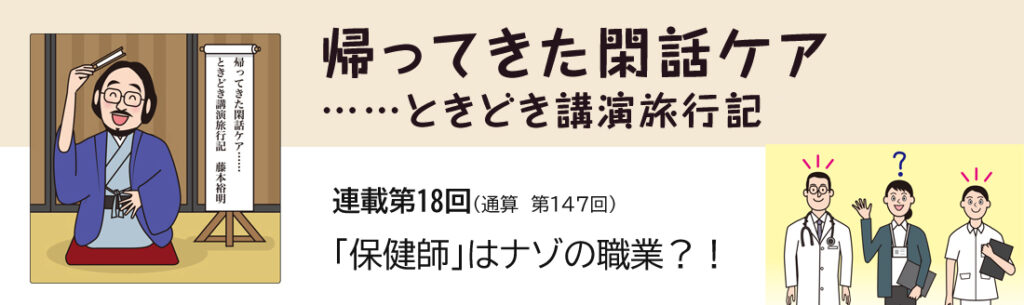
何という表題だろうか…。保健師が読者の多くを占めているというのに、一体ナニゴトか、という感じではあろうが…。
昨今、保健師相手の講演の時に「あなた達は知られていませんよ」という話をする事が多くて、この場においても、皆さんに伝えるべきなんだろうなと思った次第。
うん、文字通り「保健師」は、多くの人にとってナゾの職業なのだ。
10年位前かな。若い保健師が合コンに出た後、私に愚痴った。
「先生~! 聞いて下さいよ。……(続く)
<著者プロフィール>
藤本裕明(あさか台相談室)
分類学上は霊長目ヒト科の♂。立場上は一応、心理カウンセラーに属する。自分の所の他、埼玉県川越市の岸病院・さいたま市の小原クリニックなどで40年以上の臨床経験があるが、年数だけで蓄積はおそらく無い。むしろ、蓄積より忘却が増している気がする。
春になって桜が咲いて、それからまた気温が下がって、今年の桜は長持ちした気がする。でも、日本各地で、状況はだいぶ違うんだろうな。桜前線を追いかけながら南から北への講演旅行も楽しそうだが、そんな事ばかりしてたら本業はいつするんだって事になる。一層の事、講演を本業にしちゃうか。…なんてね。
●あさか台相談室 公式サイト
https://www.asakadai-saitama.com/
2024年最後の講演旅行は12月9日、月曜日。
前の週の金曜日に福岡から帰ってきた私は、千葉県の大網白里(おおあみしらさと)市に向かった。金曜に戻って、土曜は私の場合普通に仕事。日曜は休んで、また月曜に講演。集中する時ってこんなスケジュールになる。2週間に3回なんていう事もあった。スケジュール管理に問題があると思うが、自分がその担当でもあるから、文句も言えない…。ちなみに、奄美大島に2回目に呼んで頂いた時には、前日入りして2日目に朝と夜、3日目に朝と、2日で3講演だったが、これはもう、日常から切り離された本格的講演旅行であって、旅芸人のような気分だった。(続く)
<著者プロフィール>
藤本裕明(あさか台相談室)
分類学上は霊長目ヒト科の♂。立場上は一応、心理カウンセラーに属する。自分の所の他、埼玉県川越市の岸病院・さいたま市の小原クリニックなどで40年以上の臨床経験があるが、年数だけで蓄積はおそらく無い。むしろ、蓄積より忘却が増している気がする。
旅行記の対象以外の講演も、2月ですべて終わった。2025年度、またどこか呼んでくれる所はあるのだろうか? 現在22都道県だから、あと2か所新しい府県に呼んでもらえると、全都道府県の過半数達成。市区町村で言うと「地域保健」関連だけで70か所くらいは行っているみたい(複数回訪問地多数)。よくもそんなに呼んでもらえているなぁ…。
●あさか台相談室 公式サイト
https://www.asakadai-saitama.com/
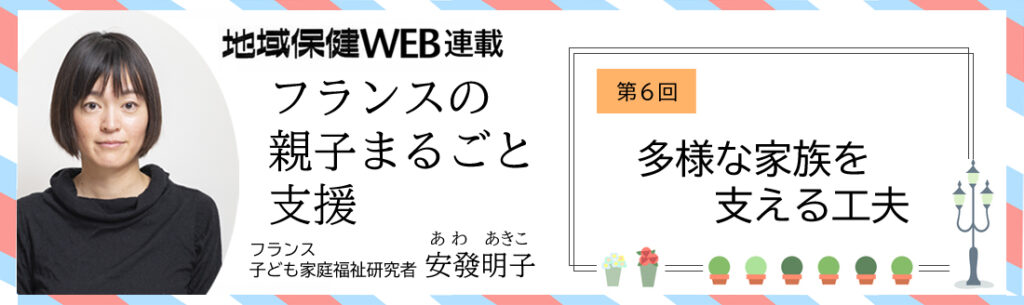
両親それぞれが現在親として子どもにできることに取り組めるよう、国が支えることを子どもの権利条約は締結国に求めています。さまざまな家族の形態に合わせ、家族を支えるフランスで取り組まれている工夫について紹介します。
<著者プロフィール>
安發明子(あわ・あきこ)
フランス子ども家庭福祉研究者。1981年鹿児島生まれ。2005年一橋大学社会学部卒、 首都圏で生活保護ワーカーとして働いた後2011年渡仏。2018年フランス国立社会科学高等研究院健康社会政策学修士、2019年フランス国立社会科学高等研究院社会学修士。フランスの子ども家庭福祉分野の調査をしながら日本へ発信を続けている。全ての子どもたちが幸せな子ども時代を過ごし、チャンスがある社会を目指して活動中。
●安發明子さん公式サイト
https://akikoawa.com/

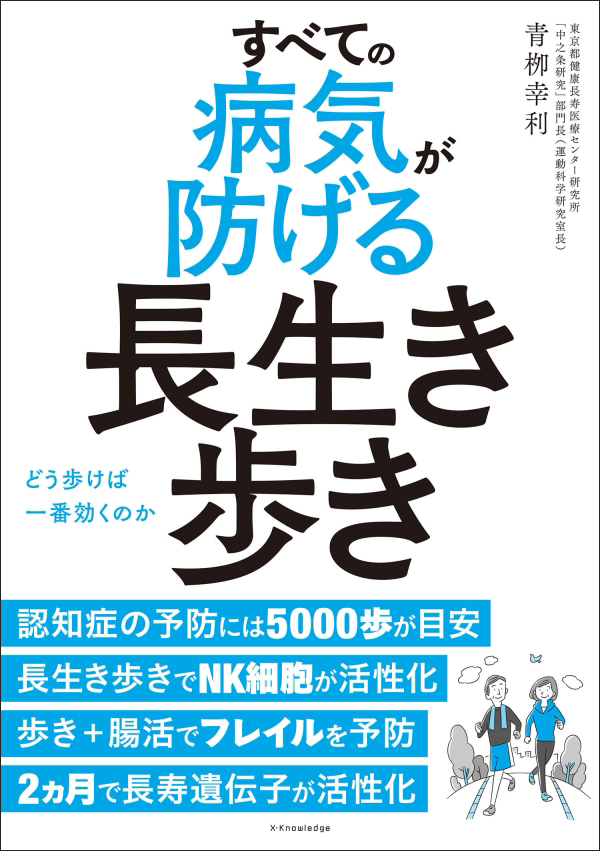 『すべての病気が防げる長生き歩き』
『すべての病気が防げる長生き歩き』