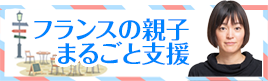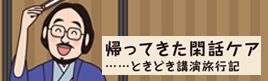帰ってきた「閑話ケア」……ときどき「講演旅行記」
第18回「保健師」はナゾの職業?! (通算 第147回)
何という表題だろうか…。保健師が読者の多くを占めているというのに、一体ナニゴトか、という感じではあろうが…。
昨今、保健師相手の講演の時に「あなた達は知られていませんよ」という話をする事が多くて、この場においても、皆さんに伝えるべきなんだろうなと思った次第。
うん、文字通り「保健師」は、多くの人にとってナゾの職業なのだ。
10年位前かな。若い保健師が合コンに出た後、私に愚痴った。
「先生~! 聞いて下さいよ。この前合コンに出てみたんですよ。そこでね、仕事の話になって『保健師』だって言ったらね、『あ、保険屋さんなんだ』って言われて。そしたら他の人が、『違うよね』って言うからホッとしてたら『保健の先生だよね』だって! もう、嫌になっちゃって、まあそんなもんですって答えちゃった」
だと。
似たような経験をした方はいませんか?
まさに、ナゾの、いや、未知の職業ではないか。10年経って、知名度は改善したか? いやいや、ほとんど変わっていないのではないだろうか。
職業は、その名称で、何となく中身がわかるものもある。
「警備員」なら、警備をしている人だな、とか、「教師」なら、教える職業だなとか。「医師」は、「医」という漢字に、癒すとか、そういった意味がある事を知っている人は少ないが、有名過ぎて問題ない。
「警察官」も、「警」と「察」それぞれの意味からの命名だが、その内容を知らなくても、有名だから誰でもわかる。「薬剤師」とか「看護師」だって、だいたいの人が、その内容を理解しているだろう。
「精神保健福祉士」とか「社会福祉士」も、何となくわかる。私のような「心理カウンセラー」も、多分、想像がつく。「理学療法士」は「理学」って何だって感じだが、リハビリの専門家だって知れ渡っている気がする。
医療関係で名称からは中身までわかりにくいのは「言語聴覚士」かな。名称から、言葉と聞く事の専門家という事はわかるけれど、呼吸とか嚥下にまで仕事の幅がある事は、名称だけでは理解されないだろう。
あと、服装でも何となくわかる場合がある。警察官や自衛官、消防士などの制服組は一目瞭然。病院では、昔ほど、医者は長白衣、看護師は白衣とナースキャップという感じではないけれど、何となく、私服とは違ったユニフォームを着ているから、医療従事者だとわかる。まあ、病院の外だとわかりにくいかもしれないが。
さて、そこで皆さんに問う。
「保健師」の「保健」って、何ですか? そして、皆さんは、どんな服装をしていますか?
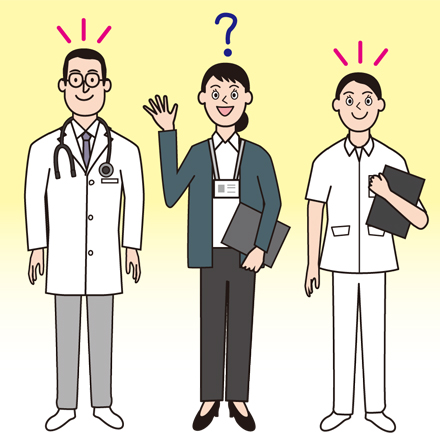
「保健」の方は、まあ、「健康を保つ」という事まではわかるだろうが、それだけであなた方の仕事を言い表してもいないし、何が専門なのかもわかりにくい。「保健」という言葉から一般の人が連想するのはやはり学校の保健室が身近かな。だから、合コンでの勘違いも起きたのだろう。
服装はどうか。日常的には制服は無い。災害の現地派遣などの場合には、「保健師」と書いてあるゼッケンのような物などを身につけていて、健康状態の聞き取りや血圧測定をしたりするけれど、白衣を着ていないから怪訝そうな顔で見られたという話も聞いた事がある。
あんなに活躍しているのにね…。
それどころか、信じがたい話と思うかもしれないが、あなた方の職場でさえも理解されていない事があるのだ。保健所や保健センターに勤務している場合は大丈夫だろうが、市役所の中だったりすると、同僚である一般の行政職員にさえ、理解されていない事もあるのだ。
「保健師ねぇ、へぇ、そうなんだ」
と言われても、何かの専門職なんだなっていうだけで、看護職・医療職だとは理解されていない場合もある。そんな馬鹿なって思う方も多いかな? でも、そう言われてみれば、心当たりがあるという方もいるのではないだろうか。
一般事務職の課長に、
「保健師だか何だか知らないが、この程度の事務仕事ができないのか」
などと、嫌味を言われた人もいるでしょう? そう、その課長は本当に「何だか知らない」のだ。
つまり、「医師」とか「看護師」は知っているのが当たり前の常識的単語なのだが、「保健師」はそうではない。何となく、わかるような気がする―という程度の単語なのだ。
しかし、もっと大きな問題がある。保健師自身は「保健師です」と言えば、自分の職業を理解してもらえているという大勘違いをしている場合が多くて、一般常識の中に自分達の職業が登場していない事に気づいていない…。世間とのギャップに気づいていないのだ。
日本の事実上の保健師活動の発端と言われているのは、1887(明治20)年に始まった「京都看病婦学校」の活動だそうだ。慈善事業として実施した「巡回看護」がそれ。つまり訪問看護だが、病院に患者が来るのを待つのではなく積極的に訪問をしたのだから、これは確かに保健師的な動きの原点と言えよう。この頃は、西洋の列強に追いつかなくちゃって事で相当背伸びした明治政府の施策により、劣悪な環境で働く工業労働者の中で結核が流行。それへの対応などが主な役割だったらしい。
その後、貧困や知識不足からの栄養失調の小児への対応、農村での健康教育など、時代のニーズに伴って紆余曲折がありながらも地域医療の担い手としての職務が確立、1937年(昭和12年)の「保健所法」で「保健婦」が誕生した。このように、歴史的にも看護師より浅い。
そして1994(平成6)年、男性「保健士」が誕生(同年に「地域保健法」制定)、2002(平成14)年に「保健師」の名称になった。つい最近だよなぁ…。
保健師は、英語ではPublic Health Nurse、直訳すれば「公衆衛生看護師」、省略形は「PHN」となる。ちなみにアメリカにもPHN相当の役割は存在するが、資格試験はなく、看護師資格を持った人間が既定の研修みたいなものを受けて看護協会みたいな所に申請すると、認証されるという事らしい。名称としては「registered nurse(登録看護師)」というそうだ。諸外国でも、保健師に相当する職務はあるようだが、日本の保健師とは仕組みが違うようだ。
それはともかく、「保健師」より、「公衆衛生看護師」の方が、医療職だとはっきりわかる気がする。
今さら名称変更もどうかとは思うけど…。
さて、私はよく、人々に対して「保健師」をこんな風に説明する。
「看護師は医学や看護学を学んで、病んだ人やケガをした人に寄り添う仕事。その看護師がもう1年、今度は人々が病気にならないためにはどうしたらいいかを勉強したのが、保健師。だから、保健師はもともと看護師なんですよ」
そう説明すると、「ああ、そうなんだ」といった反応をする市民が如何に多い事か…。
友人に看護師がいるという人は、何か病気をするとその人に相談できるから安心、とよく言う。
それくらい看護師というのは医療のプロと思われている証拠。実際のところ、例えば卒業して10年ずっと皮膚科にいた看護師が、内科の病気の相談をされたってわかるわけがないが、看護師というだけで一般人はそんな風に信頼感を持つ。
ところが、保健師にはそれが無いのだ。どうしたものだろう…。
正直、解決する妙案は私にもない。ただ、保健師としての活動をする時に、一般人が医療職をイメージする赤十字マークとか、今年の1月の「ヘビの話」で取り上げた「スターオブライフ」とか、何かそういった感じのシンボルマークを身につけたりして、医療職を外面的にもアピールした方が良いかもしれないとは思う。
だが、何よりも大事なのは、保健師自身の自覚。知られていないという事を知っておく事こそが、一番大事ではなかろうか。その上で、色々な事業などで話す度に、「保健師です」で終わらせないで、看護職だという事をアピールしよう。
例えばこんな風に。
「皆さん、私たち保健師は、もともと看護師だっていう事をご存じでしょうか? 看護師の資格を取った上で皆さんの健康を守るための勉強をしたのが私たちなんです」
そうやって、地道に宣伝していく事が何よりも大切ではないかな。
「保健師」が、ナゾの職業から、誰もが知っている職業になる日を心待ちにしている。