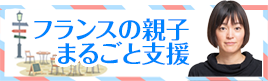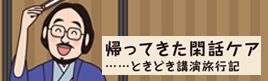帰ってきた「閑話ケア」……ときどき「講演旅行記」
第19回その線引き、大丈夫? (通算 第148回)
気象庁が関東地方の梅雨入りを発表した翌週くらいから、雨は全くなくて各地で猛暑日続出…。
はい、この日から梅雨の時期に入ったと、線を引いた途端にこれだ。もっとも、昨今の発表の仕方は、「梅雨入りしたとみられる」という表現で、後でいくらでも修正できるような発表になっているから、線引き、というほどのものでもないかもしれないが。
世の中にはいろいろな線引きがある。学生時代には、例えば100点満点で60点以上が合格点、59点以下は赤点なんていうのがあった。優秀な皆さんはそんな事で苦しんだ事はないかもしれないが、自慢じゃないがここだけの話、高校時代の私は実に見事に赤点を取っていた。英語なんか合格点を取った記憶がない。じゃ、なぜ卒業できたのかというと、古き良き(イイカゲンな)時代だったから、仲良しの英語の主任が、何とかしてくれたからだったと思う。だから、赤点をとっても苦しんだ記憶は無いのだが。もう半世紀も前の話だが、振り返ると本当にイイカゲンな話だ。
反対に、中学の時には数学の教師に呼ばれて、「お前、今学期手を抜いただろう。(通知表の5段階評定で)本当は5だけど、2をつけたからな」などという扱いをされた事もあった。手を抜いた事は覚えていないが、ひどいなって思った事は覚えている。勝手なもんだ。
点数という誰が見てもわかる線引きさえ、実際にはこんな事がまかり通っていたのだ。イイカゲンな事が許される時代だったからと思うが、さて、今はこういう事が絶対にないのかどうか。
男女の区別も線引きのひとつか。元々は、実質は別として概念上はどちらかしかなかった。
それが今ではLGBTのT=トランスジェンダーに始まり、LGBTQとか、LGBTI、LGBTAその他、沢山の親戚的な言葉があって、何がどれだか、高齢者の頭がついていけない展開になりつつある。それぞれの意味の説明は省略するので、ご自分で検索してみて下され。

メンタルの世界でも、線引きの問題が怪しくなってきた。「スペクトラム」という考え方である。
これって、元々は物理学用語で、無段階に変化している状態を指し示す表現だ。
例えば虹の色の変化。七色と言うが、赤の隣は橙色、その隣は黄色―みたいに、幼児がクレヨンで描いたみたいなクッキリとした区別は実際にはない。
メンタルの方では「自閉症スペクトラム」といった表現で使われるようになり、つまり、自閉症には無段階で色々な状態があって、重い自閉症→軽めの自閉症→健康と言える状態―という流れであり、はっきりと線引きするのは難しい。だから、スペクトラムと表現しちゃおう―という事なのであろう。統合失調症もスペクトラムとして捉えるようになりつつあるらしく、一理あるとは思うが、そういう見方をするならば、どんな病気だってみんなスペクトラムじゃないの? って、突っ込みたくなる。
身体の病気だってそうだ。血圧がいくつから上は高血圧、血糖値がいくつ以上ならば糖尿病などなど、決まってはいる。メンタルと違って、はっきりと数値が出るから説明しやすいだろうが、例えば高血圧については、1987年の日本の定義では180/100mmHgが高血圧の基準だったのだが、それが今では140/90mmHg以上になっている。しかし、地域や年齢、人種などによっても違いがあるのが普通だから、世界共通の基準というのが、実はないらしく、そうなると、日本人なら共通―というのも怪しいんじゃないかと思ってしまう。例えば背の高い人と低い人の場合、同じ基準を当てはめて良いのか。
背が高いと物理的に上の方まで血液を送らなくてはならないから、血圧は上がる。キリンなんか、上が250~300らしい。人間はそこまでではないにしても、同じ年齢でも50センチ以上も身長差がある人同士、同じ基準で語るのはおかしくないか。
さらに言えば、上が141あったら降圧剤を飲まなくてはいけないが139だったら飲まなくて良い―なんて事は、あり得るのだろうか。平均値? しかし血圧は常に変動しているはずで、その場合、24時間の平均なのか1か月の平均とすべきなのか??
ね、難しいでしょ。「その線引き、大丈夫?」って、言いたくなるのだ。
保健師の仕事で気になる線引きもある。いくつかあるが、特に気になるのは母子保健担当と精神保健担当という感じの線引きだ。事業としてはそれで構わない部分が大きいと思うが、ケースとしてだと、どうなるのだろう? あっちこっちの都道府県や市町村に伺う中で、考え方、捉え方が千差万別である事に戸惑いを感じる。どれが正しいとか簡単には言えないのだが、例えば産後うつを発症したケースはその時点から精神担当になる、という所もある。そもそも保健センターでは母子しか扱わないから、精神の病名がついた途端に保健所とか障がい福祉課の精神保健担当に移るという考え方らしいのだ。
年齢という意味では「ネウボラ」みたいに線引きを廃止しようという動きがあるのに、精神を病んだ途端に、担当が代わるというのは何なのだろう?
例えば統合失調症で幻覚妄想が激しい母親―というなら、保健師かどうかはともかく、精神のスペシャリストが担当した方が良いし、母子保健担当と精神保健福祉士が協調介入するなんていうのが現実的であるとは思う。
しかし、今や精神科の敷居が低くなったせいもあり、世の中には「うつ病」「適応障害」「不安障害」などの病名を持つ人がウジャウジャ居る。なのに、そういう病名がついたら母子保健担当から外れて精神担当に移るっていう線引きは、現実的なのだろうか。
保健師の原点のひとつが母子保健活動である事は存じているが、現代においては精神の問題も、保健師にとって無視できない基礎的な領域と言えるんじゃないかな。古典的な精神病だけが精神医療の対象という位置づけではなくなっている現代においては、誰もが経験し得るトラブルのひとつとして、精神の領域をとらえ直す必要があると思うのだ。
ケースについては地区担当制で、その地区であれば精神でも母子でも同じ保健師が持つ―という所もある。でも、それがつらいという保健師の声も聞いた事がある。 でもね、食わず嫌いみたいな事を言わないで、学んでみてほしい。案外、色々な発見があって面白い世界でもあると思いますよ。
じゃ、どうやって学べば良いか? 学問としての精神医学や精神看護学を学ぶというより、出来れば事例検討などで、精神科医や精神保健福祉士や心理職など、違う職種の見解に触れられるような研修を、全国的に展開して欲しいなぁ。そういえば、だいぶ昔、相談室で主催して1回だけやった事があるけど、それも結構好評でしたよ。地域のいろいろな職種が集まって、なかなか面白かった。
ケースへの対応をどこまでするかという線引きも難しい。私が日常的に関わっている地元の市で、クレイマー的ケースからの電話対応の話が出た。電話に出た相手が事務職でも保健師でも無関係に話し出すと止まらない。15分という区切りをつける方針だがそれで良いかどうか、といった話。
皆さんの所はどうしていますか?
市町村の職員は、人口が3,000人でも30万人でも、それらの人達に対して対等にサービスを提供しなくてはならない。限られた電話回線を1人の住民に独占されて1時間も2時間も話を聞いてしまったら、他の住民と対等な扱いと言えるかどうか。
単純計算で、5回線の電話があって、1日8時間の電話対応ができるとして計算すると、住民に対して市町村が用意できる時間は実質1日あたり2,400分になる。3,000人規模の小さな自治体だったとしても、1人当たり1分も取れない。実際には3,000人全員が電話をしてくるなんてあり得ないから、仮に全住民の1割が電話をかけてくるとして、300人。これで1人あたり8分の配分になる。
いやいや、実際にはもっと少なく0.1%だよ―という統計があったとする。30万人規模の自治体の場合、0.1%でも300人。電話回線が10回線あったとして1人16分という計算になる。
もちろん、長電話になる対応がどうしても必要という事態が無いわけではない。だから杓子定規に時間を守る事だけが大切ではない。だが、さっきの話のようにクレイマーのようなケースの場合には、線引きが必要ではないか。じゃ、何分が妥当なのか?? ね、線引きはやっぱり難しい。
私の生活の中にも線引きはあるかって? うん、あるとは思う。でも、ピシッとした直線はないかもしれない。グニャグニャ曲がっていたり、太さが違ったり、ところどころ消えてたり、あっちこっちに移動したりしているような気がする。どうにもイイカゲン過ぎて、線とは言えないかもなぁ…。