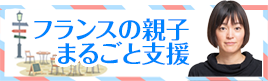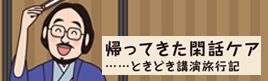なな先生のことばの発達教室
第14回 ことばの遅れへのアドバイス 「読み聞かせ」と「ことば掛け」だけでいいの?
ことばの発達について悩む保護者の方へ、「読み聞かせ」や「ことば掛け」といったアドバイスはよく耳にするかもしれません。しかし、本当にそれだけで十分なのでしょうか? この回では、絵本の「読み聞かせ」や「ことば掛け」にこだわりすぎることなく、子どもの特性や発達段階に合わせた関わりの大切さについて、言語聴覚士としての経験を交えながら考えていきます。
絵本はもっと自由でいい
絵本は、ことばの発達支援において欠かせない存在としてよく取り上げられます。保護者にとっても、「絵本をたくさん読んであげましょう」というアドバイスはおなじみかもしれません。でも、「せっかく選んだ絵本なのに、何度トライしても全然聞いてくれないんです……」保護者の方から、こうした声を聞くことがよくあります。
「ちゃんと読まなきゃ」と思っていた私
新人の言語聴覚士として小児のことばの支援の現場に出始めた頃の私は、絵本の読み聞かせをどう扱えばいいのか、正直戸惑っていました。
せっかく準備して持っていった絵本を、お子さんが最後まで聞いてくれません。ページをめくるのに夢中だったり、途中で立ち上がってどこかへ行ってしまったり、気に入ったページだけを繰り返し見たり……。
「ちゃんと読めなかったな」とがっかりしていた当時の私に、今の私から伝えたいことがあります。
――そもそも、絵本を"ちゃんと読む"ことが目的じゃなくてもいいんだよ、と。
いつのまにか、絵本は"遊び道具"に
たとえば、2歳になったばかりのうちの息子は、ついこのあいだまで本棚から絵本を1冊ずつ出してはまたしまう、という遊びに夢中になっていた期間がありました。ほかには本を斜めに傾けて、その上に車のおもちゃを走らせ本を"道"にして遊んでしまったり。これは今も時々しています。特におもしろかったのが、バスの絵本を2冊開いて「ブッブー」と言いながら、絵本のなかのバス同士を追いかけっこさせていた様子です。
遊びの創意工夫を感じたのは、消防車の絵が出てくるページを開いて、そこにミニカーの消防車を乗せ対応させたり、動物の顔が大きく描かれたページを開いたり閉じたりしながら「いないいないばあ!」をするような思い付きです。このように、本来の絵本の使い方から離れ、じつに自由です。
「絵本を読む」より「絵本で一緒に楽しむ」
言語聴覚士の仕事でも、気が付けば今では、絵本を最初から最後まできちんと読み聞かせようとするような言語指導は、ほとんどしなくなりました。
たとえば、特定のページに強く惹かれるお子さんには、そのページを目指して一緒にどんどんページをめくっていくようにします。そして、1回だけで終わるのではなく、2〜3回同じことを繰り返します。「お気に入りのページに行くまでのプロセス」を遊びとしてしまう楽しみ方ですね。
また、絵本の表紙だけをじっと見つめていたり、広げた絵本を床に並べて眺めるお子さんもいます。このようなときは、無理に中身を読もうとせず、「バナナだね」「あかいくるまだ」などと表紙を眺めてお話を広げることもします。お子さんが絵本を渡してくれる「はいどうぞ」だけをひたすら続けることもあります。

紙面に書かれている文字通りに読むことはほとんどせず、子どもの反応に合わせて変えていきます。いわゆる読み聞かせではなく、子どもにお話を先導してもらうこともしばしばです。
読み聞かせにこだわらなくても大丈夫
こうしたわけで、絵本は「読む」だけではなく、「一緒に遊ぶ」「一緒に見る」「一緒におしゃべりする」ための素材になることがあります。絵本ははじめのページから順番にめくって読むもの――そうした大人側の勝手な思い込みから少し離れてみると、積み木やミニカーと同じく、"おもちゃ"として絵本で楽しく遊ぶお子さんの姿を見つけられます。
それから、固定観念に縛られずに絵本を自由に使うことで、かえって徐々に絵本に親しめるようになってくることも多いものです。
読み聞かせも「万能」ではない
読み聞かせがことばの発達に有効である、という考え方はよく知られています。私自身も、絵本が語彙を広げるきっかけになったり、親子のやりとりを豊かにしてくれる素晴らしい道具だと思っています。
でも、どのお子さんにも必ずしも"読み聞かせ"がフィットするとは限りません。
たとえば、一度に注目できる時間が短いお子さんに長い絵本を読み続けても、周囲に気を取られて内容を理解しないまま終わってしまうことがあります。絵や写真は、平面で表現され、実物と異なる特徴が描出されていることもありますので、まずは絵本ではなく実体験から理解したほうがよいこともあります。見る・聞く以外の感覚もフルで使い、触れたり匂いをかいだり汗ばむ湿度や温度を感じたりといった体験・経験がまだまだ概念形成(ものごとはこういったものだと本人なりに理解を固めていく心の働き)に重要な発達段階にそのお子さんがいる場合には、絵本以外のアプローチを選択したほうがよいでしょう。
読み聞かせは、手段のひとつであり、万能な手段ではありません。ことばがまだ出てこない・ことばが遅いといったお悩みへのアドバイスとして適さないこともあるのではと個人的には考えています。
「親の努力不足」へのすり替えに注意
「もっと話しかけてください」「動画の見せすぎでは?」といったアドバイスが、結果的に「保護者の努力不足」と捉えられてしまっている……。そのようなご経験はありませんか? 私たち支援者にその意図がなかったとしても、受け取る側にとっては「自分が悪い」と感じさせてしまう可能性があるんですね。
ことばの発達には、その子の持って生まれた特性や発達のスピード、周囲との関わりの質など、さまざまな要素が複雑に関わり合います。そのため、親御さんが十分にことば掛けをしていても、ことばがなかなか出てこない子はいます。
仮に、支援者から見て、実際に「ことば掛けが不足している」「動画を見せすぎている」に該当するだろうケースであったとしても、保護者を責めるニュアンスとして伝わってしまうのはやっぱりもったいないと思います。
たとえば、動画視聴が多いご家庭があったとしても、それは「保護者の怠慢」とは限りません。お子さん自身が動画を強く好み、対応しないと癇癪を起こしやすいということであったり、きょうだい児の育児と並行して関わるには、いったん動画を見せるしかない、というような日常の工夫だったりすることもあります。
また、お子さんの反応が乏しいためにことば掛けを保護者があきらめてしまっているという状況が見えてくることもあります。
そうしたケースでは、お子さんを理解する視点の広がりや関わり方のヒントがあればもう少し行動に移せそう、ということがあるはずです。
大切なのは、「もっと頑張ってください」と言うことではなく、
「今できていることをどう活かすか」
「この子に合う関わり方は何か」
「どんなことからであれば、変えていけそうか」――
こうした問いの答えを一緒に見つけていくことだと思います。
「ことば掛け」は"質"の調整がカギ
また、「ことばが出ていないならば、ことばをもっと増やそう」と焦ってしまうことがあるかと思います。でも、"ことば掛けの量を増やす作戦"では、もしかしたらお子さんに合わせたことば掛けになっていないかもしれません。
お子さんが個別に持つ理解語彙・フレーズのレパートリー、すなわち「伝わることば」「分かることば」を見極め、それらを子どもの聞く姿勢が整った瞬間――"入る"タイミングで使っていくことが、ことばを育てる上でとても大切です。
適切なことば掛けに調整したその結果、ことば掛けの"量"はむしろ減っているように見えることもあります。でも、その分、やりとりの「充実度」が濃くなり、お子さんの理解が進み発語につながります。
フラッシュカードはことばの"根"を育てられるか
早期教育や知育の文脈でたまに見かける「フラッシュカード」についても考えてみましょう。テンポよく絵や写真のカードをめくって見せながら、「りんご」「いぬ」「くるま」と語彙を提示するスタイルです。また、ことば掛けを伴わずに、ただカードを次々と見せていくだけの使い方をしている例も散見されます。
一見、効率よく語彙を教えられているように思えますが、本当にことばの理解や使用につながっているのかという点では慎重な検討が必要です。
たとえば、カードの「りんご」を繰り返し見たとしても、自身の体験と結びついたイメージが呼び起こされたり、「食べたい!」や「あまり美味しくなさそうだから今はいいや」などと結びついていたりしなければ、ことばとしての意味は育っていません。
実際のやりとりや経験の中で「使いたい」という思いが生まれてこそ、ことばは根を張ります。
また、その場での実体験を伴わない絵カードでのラベリング(名前を言うこと)が安定して可能になるのは、発達段階ではもう少し先のことです。
フラッシュカードという道具が悪いのではありません。すでに知っている・使えることばを定着させるときには非常に役立つツールだと思います。ただ、それが"ことばの根っこ"を育てる素材になり得るかどうかは、使い方やお子さんの発達段階との相性によって大きく変わります。
1歳6か月健診「ワンワンどれかな?」が難しい理由
1歳6か月健診では、「ワンワンどれかな?」という課題が出されることがありますね。複数の絵が描かれた図版を提示し、「ワンワンはどれ?」と聞いて、子どもが犬を指差せるかを確認するものです。
でも、これがうまくできない子は少なくありません。もちろん、この項目で観察したい「指さし」や言語理解の獲得が進んでいない可能性もあるのですが、それだけとは限りません。健診という非日常的な環境では緊張して普段の実力を発揮できないお子さんがいるのは当たり前のことです。
実際に、言語聴覚士の初期アセスメントでは、まずはプレッシャーをかけない遊びやただ過ごすことを通して関係づくりを丁寧に行った上でこうしたアセスメントを実施するのが通例です。また、ひとつの課題や検査項目ができなかったという単一の反応から評価をすることは避け、別の方法でアセスメントできないかを探っていきます。
1日の中で多くのお子さんが訪れる慌ただしい健診会場ではこのような流れは取れないため、場慣れや相手慣れが必要なお子さんにとっては認知発達・言語発達をアセスメントするところまで達成できないのは当然のことなのです。
1歳6か月健診、喋るけれど「ワンワンどれ?」はやらなかった
ちなみに、うちの息子は1歳6か月健診で「ワンワンどれ?」の指差しに応じることはできませんでした。後学のために、健診後も定期的に「複数の選択肢から言われたものを指差して選ぶ」ができるかどうかを確認していたのですが、安定して成立するようになったのはようやく最近になっての1歳11か月頃でした。はじめてことばを話したのは1歳1か月ごろで、健診を受けた時期にはすでに複数の単語発話が増えてきていた時期でした。つまり言語理解や言語表出がある程度進んでいる段階の児であっても、「選択する指差し」は難しいということもありそうです。
ひとつの課題で、すべては分からない
もちろん、「できなかったけどたいした問題じゃない、大丈夫」と単純に言いたいわけではありません。ただ、たったひとつの検査項目だけで、その子のすべてが判断できるような"万能な検査"は存在しません。健診に向けて「ちゃんとできるか不安で仕方なくて当日が憂鬱……」と、漏らす保護者の方の声を聞くこともあります。
だからこそ、私たち支援者が、検査の意味や背景、そして"できなかった"をどう捉えるかについて丁寧に伝えていく必要があると感じています。
おわりに
ことばの発達を支える上で大切なのは、「何を」「どれだけ」伝えるかだけでなく、「どんなふうに」「どんな場面で」関わるかです。
絵本も、動画も、カードも、使い方しだいでことばのきっかけになります。でも、道具そのものに魔法の力があるわけではありません。
子どもの気持ちに寄り添い、やりとりを楽しみながら、少しずつことばの根っこを育てていく――そのような関わりこそが、ことばを育むいちばんの土台なのだと思います。
なお、この連載の第10回では「繰り返しのある遊び――「ことばのシャワー」や「たくさんの読み聞かせ」に代わるアドバイス」というテーマで執筆しております。どんなアドバイスがいいの? と疑問に思った方は、ぜひそちらも併せてお読みください。
おすすめの本
『発達が気になる赤ちゃんにやってあげたいこと 気づいて・育てる超早期療育プログラム』
著者:黒澤礼子(健康ライブラリースペシャル 講談社)2017
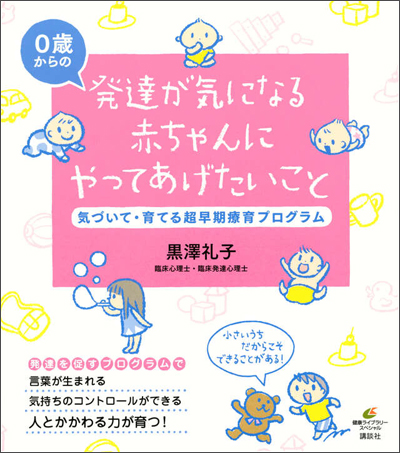 「言語訓練って椅子に座って先生の言うことが聞けるようになってからやるものじゃないの?」と聞かれることもありますが、いちばん悩みが深刻なのは、1,2,3歳頃のことばがなかなか出ないお子さんのご相談です。こうした、"机上課題以前" "読み聞かせ手前"のお子さんに対して何をしてあげればいいの? は助言する立場として非常に悩むところだと思います。この本では、0歳から赤ちゃんにしてあげられることを発達の順序に従ってやさしく提案してくれています。小さなお子さんのいるご家庭の発達相談に乗られる支援者の方々は、ぜひ手元において日々ご参照ください。
「言語訓練って椅子に座って先生の言うことが聞けるようになってからやるものじゃないの?」と聞かれることもありますが、いちばん悩みが深刻なのは、1,2,3歳頃のことばがなかなか出ないお子さんのご相談です。こうした、"机上課題以前" "読み聞かせ手前"のお子さんに対して何をしてあげればいいの? は助言する立場として非常に悩むところだと思います。この本では、0歳から赤ちゃんにしてあげられることを発達の順序に従ってやさしく提案してくれています。小さなお子さんのいるご家庭の発達相談に乗られる支援者の方々は、ぜひ手元において日々ご参照ください。