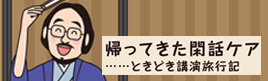【2025/9/27イベント開催報告】地域保健×「まちの保健室」ITOGUCHI 「じょっぱり 看護の人 花田ミキ」上映会&トークセッション “わたしたちの、もったらKorosuna運動”
地域保健編集部は、保健師映画応援プロジェクトおよび保健師の認知度の向上を目指す活動として、青森のナイチンゲールといわれた実在の保健師、花田ミキさんの波乱万丈の生涯を描いた映画「じょっぱり 看護の人 花田ミキ」の上映会とトークセッションを開催しました。
当日は、関係者を含め約60名での映画鑑賞となりました。たくさんの方々と、映画やゲストの皆さまのお話を共有でき、とてもあたたかな時間を過ごすことができました。心より御礼申し上げます。
開催概要
「地域保健×「まちの保健室」ITOGUCHI
「じょっぱり 看護の人 花田ミキ」上映会&トークセッション」
- 日時:2025年9月27日(土) 13時30分(開場13時)~16時30分
- 会場:株式会社シンゾーン 本社ショールーム(表参道)
- 定員:50名(先着順)
- 主催:「まちの保健室」ITOGUCHI(一般社団法人FLEXIBLE)/地域保健の共催
- 協力:株式会社シンゾーン/公益社団法人いちご言祝ぎの杜
開催内容
- 映画上映
「じょっぱり 看護の人 花田ミキ」(90分) - トークセッション
「わたしたちのもったらKorosuna運動」“明日のために昨日を語る”それぞれの立場から- ゲスト
鎌倉幸子さん(映画プロデューサー)
和泉慶子さん(書籍「東京保健師ものがたり」著者・元特別区保健師)
相馬有紀実さん(俳優)
染谷裕之さん(株式会社シンゾーン代表取締役/公益社団法人いちご言祝ぎの杜代表理事)
- ゲスト
- 交流会
同会場にて、参加者同士の交流会(参加自由、軽食つき)
開催レポート
地域保健編集部は2025年9月27日(土)、まちの保健室ITOGUCHIさんとの共催で、映画「じょっぱり 看護の人 花田ミキ」の上映会とトークセッションを開催しました。
会場は、表参道にあるシンゾーン本社、ショールームです。アパレル企業であるシンゾーンは「ファッションとウェルフェア(福祉)の架け橋」をミッションに掲げ、社会的養護下にある子どもたちや、矯正施設(女子少年院)にいる少女たちのサポートを積極的に行っています。このたび本イベントの主旨にご賛同いただき、素敵なショールームを貸してくださいました。
この日は定員50名のところ、関係者を含め約60名の方々にお集まりいただきました。開場するや続々と参加の方々が来場され、上映時間まで映画の関連資料や雑誌『地域保健』創刊号などの展示をご覧いただきました。
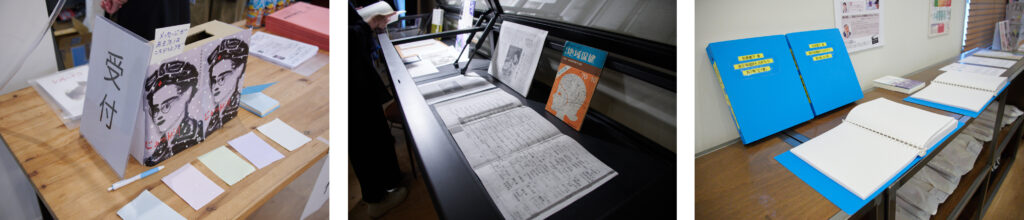
上映会
当日の欠席はほとんどなく満員御礼、上映会は定刻通りに始まりました。映画の主人公である花田ミキさんは、従軍看護師として三度戦地に赴き、戦後、保健師となった人物です。当時ワクチンがなかったポリオ(小児まひ)の治療法と予防の普及、へき地保健師派遣制度の創設、乳幼児の死亡率減少を目指す「もったらころすな運動」などに取り組み、公衆衛生に尽力されました。
映画は、シングルマザーとして息子リクの子育てに追われる20代のちさとが、現役をリタイアし80代となったミキさんと出逢い、心を通わせていく物語です。二人の交流を軸に、ミキさんの波乱万丈の生き様がいきいきと描かれていました。
映画のタイトルである“じょっぱり”とは、青森(とくに津軽地方)の方言で、「頑固者」「強情っ張り」という意味です。「がまん強い」「粘り強い」といった肯定的な意味にも使われ、青森県民の気質をあらわす言葉として、広く知られています。
ミキさんはまさに、生涯、目の前にある命とまっすぐ向き合い続けた人でした。映画終盤、会場ではすすり泣く声も聞かれるなど、会場一体となってミキさんの世界に入りこんだ90分でした。
終了直後、会場は大きな拍手に包まれました。
〈トークセッション〉わたしたちのもったらkorosuna運動 それぞれの立場から
「命を阻むものは、すべて悪」という信念を貫いたミキさんの生き方から熱いメッセージを受け取った後、ゲストらによるトークセッションが行われました。「現代に生きるわたしたちの“もったらころすな運動”」をテーマに、4名のゲストに語っていただきました。

【ゲストスピーチ】
- 鎌倉幸子さん(映画プロデューサー)

五十嵐監督は「真実を知って、嘘をつく」が信条です。真実を深めて、深めて、深めて、そして映画という物語に落とし込みます。「じょっぱり」の制作にあたり、わたしはクラウドファンディングによる資金集めや協力者探しに奔走する一方、監督とともに、花田ミキさんに関する資料、当時の世相から戦争、そしてそこに存在する看護師、保健師という人や職業について徹底的に調べました。
「保健師のことを知るには、実際の保健師さんにお会いし話を聞かねば」という監督の強い思いを受けとめ、保健師さんへのヒアリングの場をつくってくれたのが、「地域保健」の松岡さん、「まちの保健室 ITOGUCHI」の村瀬さんでした。
花田ミキさんが生涯を捧げた命への取り組み。その先にわたしたちは生きています。劇中のミキさんの言葉にあった「自分の生き方を選択できるようになった幸せ」は、これからはわたしたちが守っていかねばなりません。
花田ミキさんがご自身の生き方を通じて未来に伝えたかったメッセージが、皆さんに届き広がっていくことを願っています。
- 和泉慶子さん(東京保健師ものがたり著者/元特別区保健師)

わたしは東京都の特別区などで、保健師として通算35年ほど勤めました。自分が経験した事を次の世代に伝えたいと思い、職場で実習生の受け入れや新人研修のときに、空いた時間に読んでもらえるように書き始めました。それをベースに執筆したのが地域保健で連載した『東京保健師ものがたり』で、その第8話「妊娠してませんから!」は、“もったらころすな”がテーマです。
「離れて暮らす16歳の娘が妊娠、出産も近いようだが、事情があり会えない。様子をみにいってほしい」――そんな電話が主人公の保健師のもとに入ります。訪問してみると、ドアの向こうには青白い顔をしたごく若い女性の姿が。お腹も明らかに大きい。ところが女性は「わたし、妊娠してませんから!」と強い口調で保健師の訪問を拒みます。作中では、そこから保健師が女性との信頼関係を築いて母親と子どもの命を守る支援へとつなげていきます。
保健師には、本人の話にじっくりと耳を傾けて相手の心を開き関係を構築する力、生活状況や家族関係などを把握し、その人に合わせた支援プログラムをつくり実行する力が欠かせません。
AIがなんでも答えを出してくれるという時代になりつつありますが、保健師には、一対一の対話を通じた支援がいまも、これからも求められると思っています。
花田ミキさんが残したことば「明日のために昨日を語る」を私も実践していきたいです。
- 相馬有紀実さん(俳優/鈴木治子役)

鈴木治子役を演じました。実は、映画の撮影当時、わたしのおなかには赤ちゃんがいました。妊娠中でしたので映画の出演を依頼されたとき、実は少し迷いましたが、監督の熱い思いに惹かれて安定期に撮影することも分かり、出演を決めました。
監督はじめスタッフの方々は、撮影中ずっと、わたしの体のこと、おなかの赤ちゃんのことを気遣ってくださいました。おかげさまで安心して最後まで楽しみながら演じきることができました。その後、無事に出産、子どもは今年、2歳になります(会場から拍手)。
撮影前に保健師さんたちと話す機会をいただいたのですが、なぜかとても安心できてあったかい気持ちになれたのを覚えています。「わたしには、自分のことを大切に思ってくれ、温かく接してくれる人たちがいる」そう思えることって、人にとってなにより生きる力となるのではないでしょうか。
わたしは役者をしながら、映画制作もしています。テーマは、やはり“いのち”。ぜひ、これからも皆さんと映画を通じてつながっていきたいです。
- 染谷裕之さん
(株式会社シンゾーン 代表取締役/公益社団法人いちご言祝ぎの杜 代表理事)
この映画を観たのはきょうが2回目です。はじめはなかなか想像ができなかった看護の人の仕事も、映画を観た後は素晴らしい仕事だなと思いました。人生の選択ができない状況に置かれた方々がいたこと、そして、いま自分たちで選択できることは、それ自体が幸せなことだと分かりました。映画を観た後に、私の亡くなった母が妊娠した方、出産された方の相談に乗るような仕事をしていたことを思い出し、そんな接点もあったのかと気づきました。
私はいちご言祝ぎの杜の活動を市ヶ坪さゆりさんと一緒に取り組んでいます。市ヶ坪さんは、12年程前から「イチゴイニシアチブ」という子どもたちにお祝い、慶びを届ける活動をしている方ですが、私は市ヶ坪さんに会い、この人の力になりたい、何かの、誰かの役に立ちたいと思いました。どうせやるなら、ひとりでは何もできない子どもの力になれることをしたいと考え、市ヶ坪さんがやっていることが素晴らしいと思ったので、そのまま同じことをやろうと、3年前に一般社団法人いちご言祝ぎの杜を立ち上げ、昨年は公益社団法人となりました。
また、シンゾーンでは、「ファッションとウェルフェア(福祉)の架け橋」になれることを目指しています。ファッションと福祉は両極端のように思われるかもしれませんが、実は案外近いところにあると感じています。具体的な活動としては、女子少年院の愛光女子学園と協働し、少女たちが授業でつくったレース編みの作品をシンゾーンで商品化するなど、少女たちの更生に寄与する教育プログラムに関わっています。また、年に2回洋服の譲渡会を行っていて、社会的養護下で暮らす子どもたちに、スタイリストと一緒に洋服を選ぶ体験などをしてもらっています。
いまのわたしができることとして目指しているのは、就労支援です。社会的養護下で暮らす子どもたちの就職先のひとつにシンゾーンで働くという機会をつくり、社会人として彼ら、彼女らが自立していく後押しをしたい。そして将来的には、その取り組みをファッション業界全体に広げ、ファッションを職業にする子どもたちを増やしたいと考えています。
劇中で花田ミキさんがおっしゃった、「誰もが人生の選択ができる」社会づくりの一環として、将来つきたい職業につける、やりたい仕事ができるなど人生の選択肢を増やすことにつながればと思います。
そう、最後になりましたが、花田さんとわたしの共通点がたったひとつありました。
それは、パチンコです!
染谷さんの最後の一言で、会場はどっと笑いに包まれ、大きな拍手が沸き起こりました!
【参加者ディスカッション&交流】
共催の「まちの保健師」ITOGUCHIの代表である村瀬さんからは、2025年1月に仙台で行ったアートイベント「なぜ生まれたのか知りたい(ナゼウマ)」で、イベントに参加してくれた方の思いをのせたナゼウマ七夕に協賛した関係から、七夕飾りの作り手である職人の鳴海幸一郎さんを紹介いただきました。会場でも、実際に七夕まつりに掲出した飾りの写真やパネル、ナゼウマ七夕に使わせてもらった東日本大震災の復興シンボルである「仙臺七夕祈織」という仙台市の児童生徒が一人一枚追った折鶴を集めた飾りを再生した紙の説明や見本などを展示していました。鳴海さんは七夕職人としては6代目に当たるそうですが、七夕の伝統をどう伝承していくかということを視野に入れ、今後は自身も語り部、作り手として活動されるということで、街づくりサポート株式会社を7月1日に立ち上げたそうです。ITOGUCHIさんもたまたま7月1日が開所日ということで、新たな縁を結べた開所記念イベントとなりました。

また、来場者の中から、映画のパンフレットのデザイナーをされた方、映画製作にあたっての保健師ヒアリングに協力してくださった保健師さんたち、さまざまなご縁から参加された方などを司会からご紹介させていただきました。トークセッション終了後は、同会場で参加者同士の交流会を任意参加で行いましたが、うれしいことに、ほとんどの方が参加してくださいました! 飲み物などを片手に皆さまリラックスムードで、映画のこと、互いの活動のことなど話に花が咲きました。予定時間を延長し、会場は日が暮れるまでおおいに盛り上がりました。


シンゾーンの皆さまには、会場を貸していただいたばかりでなく、交流会での飲み物、軽食までご提供いただきました。この場に集った方々へのホスピタリティ溢れるあたたかいお心遣いに深く感謝申し上げます!
[写真:Tomonori Nambu]
参加者アンケートから
【映画のご感想】
- 保健師の大先輩の活動を映画で知る機会になりました。看護師はみんな知っているけれど、「保健師って何をする人?」という認識がまだまだ多い中、花田さんは足を使って訪問して地域の現状を理解し、地域に合わせた支援をする人だったのだなとあらためて思いました。
- 花田ミキさんのように闘ってこられた方がいるから、今日の私たちがあるとあらためて痛感しました。
- 保健師はあたりまえの弊害を変えていくお仕事だと思ってきました。まさに花田ミキさんはそんな人だったのだなぁと。あたりまえを変えていくことは、傍目にはいつのまにか変わっていると感じられるものだけれど、実はその裏には哀しい想いをエネルギーに変え、熱量とエビデンスで立ち向かうチカラがいる。私たちにもその保健師のDNAはつながっていると思います。まだまだ自分にもやることあるなと思いました。
- 保健師という職業の役割や存在意義などについて再認識できました。男尊女卑が横行する時代に、弱い存在の女性や子どもを守る花田ミキさん、治子さんの信念に敬意を表します。ちさとさん、りくさん、ミキさんの縁や関わりに胸が熱くなりました。
- 心から感動しました。途中涙がこみ上げるシーンも。人間は悲しみを避けて生きてはいけませんが、漁師さんのご家庭のお話は人生とはなんなのか? 何のために生きているのか? 深く考えさせられました。全てに意味があると思いますが、自分が同じ立場だったらどうだろうか? いま、恵まれすぎている環境に甘えず、感謝の気持ちで日々生きていかなければと思いました。そして医療に関連するお仕事をされている方々の想い、尊さをあらためて感じました。特に、まだまだ医療が整っていない時代に、命懸けで奮闘されてきた花田さんやたくさんの無名な人たちの存在があっていまがあるのだと教えていただきました。感謝です。
- 保健師は、年齢や性別に関係なく、子どもも大人もみんなの命を守る使命感で活動していたと思います。しかし、自治体に所属していると、国策や首長の方針に従わざるを得ない場合もあり、それが健康を衛ることと必ずしも一致しない時に苦悩することになります。「もったら殺すな運動」がどのように根付き、乳児死亡の減少に貢献したのか、あらためて調べてみたくなりました。
- 花田ミキさんの情熱と実践力に感動しました。二度とない人生、このように生きたいです。
- ミキという存在がとても重要なのは言うまでもないことですが、いまの世の中がよくならないのは、治子のような存在が少ないせいではないかと思いました。
- 今回、二回目の鑑賞でしたが、第三の人生をスタートしたところでしたので、とても身に入ってきました。ミキさんの終活からのシーンは、特に、響き、これからの人生に活かしたいです。
- 花田ミキさんの功績を伝える映画でありながら、コロナ禍で製作されたということもあり、看護職の家族の心情まで描かれた良作。保健師の仕事は、「普通」をまもる仕事だといわれますが、予防がうまくいったときには誰にも知られず、ほめられることもなく、表面的には何も起こっていなかったように日々が過ぎていくものです。でも、そんな何も起こらない日常こそが愛おしいものだと再認識しました。子どもの笑い声や、緑に包まれた景色を見るたびに、この幸せを忘れないようにします。なかなか表現しにくい保健師の仕事を作品にしてくれたことに心より感謝します。
- 幸運なことに何度か鑑賞する機会があり、今回も心を揺さぶられた。特に「もったら殺すな!!」のシーンと「ラッセーラー、ラッセーラー!」のねぶた囃は胸にこみあげるものがあり、何度でもで聴きたい。
- 戦後間もない頃の保健師さんの苦心された点がよく分かりました。いまの公衆衛生の充実につながっていると感じました。
- 保健師さんについては漠然としたイメージしか持っていませんでしたが、この映画を通して、当時の社会の中で人々に寄り添い、ひたむきに地域を支えてこられた姿に胸を打たれました。
- 時代背景も含め、あの時代を生きた方々の力強さを感じ、とても印象に残りました。
【トークセッション・交流会のご感想】
- 普段なかなか知ることができない、監督や俳優、プロデューサーなど、映画に携わる人の話が生で聞けるよい機会でした。
- 異なる業界の方々がそれぞれの視点で語られていてよかった。保健師さんの存在がもっと世に知られるように、自分にも何かできることがないか考えていきたいと思います。
- 想像もしていなかったようないろいろな活動があることを知ることができました。実際の保健師さんのお話は、映画の続きを見ているような感じがしました。
- バラエティに富んだゲスト方々のお話は、それぞれ深く味わいのあるもので参加できてよかったです。また、ゲストの方や参加者同士で話せる時間があるのもうれしかったです。ゲストの話はもっと聞きたいものが多く、次があるならまた参加したいです。
- 撮影の苦労や、保健師とは直接接点がない方々とのつながりを感じることができました。上映会を企画していただきありがとうございました。地域保健は私が保健婦学生の時からの参考書です。もう40年以上前です。これからもさまざまな情報発信をお願いします。
【ご質問】
- 花田ミキさんに関する本を購入したい場合は、取り扱っていますか?
(回答)地域保健編集部では取り扱いがございません。販売元や参考リンクをご案内いたします。ご活用ください。- 『命を阻むものはすべて悪 花田ミキという生き方』
東奥日報社 A5判・約200頁・定価1,320円(税込み)
詳しくはWeb東奥:東奥日報の本・電子書籍ページからご覧ください。 - 映画『じょっぱり 看護の人 花田ミキ』パンフレット
詳しくは株式会社ストームピクチャーズ公式サイトからお問い合わせください。 - 『~20世紀におくる~鎮魂のうた』著者:花田ミキ(自費出版)
「じょっぱりー看護の人花田ミキ」命の尊さを綴る映画制作プロジェクト(READYFOR)このプロジェクトの活動報告ページで、ボランティアの方々が文字起こししてくださった花田ミキさんの著作をご覧になれます。
- 『命を阻むものはすべて悪 花田ミキという生き方』
自主上映会の様子が読売新聞(2025年9月30日朝刊:都内版)に掲載されました!
.jpg)
この記事に関する問い合わせ先
株式会社東京法規出版 地域保健編集部
E-mail:chiikihoken@tkhs.co.jp
電話:03-5977-0353
リンク